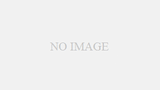ebikani
これからさらに人口が減り、少子高齢化が進むことは確実。だからこの能登だけでなく、全国の集落は集団移転を考えないといけない。たった数人、数十人のために、電気、水道、ガス、道路などのインフラを何億、何十億かけて維持するのは難しい。災害が起きたら尚更。こんな集落が全国そこら中にある。生まれ育った場所や、先祖代々の土地ということで離れたくない人も多いと思う。だけど、現実的に考えないといけない。この問題は今後確実に大きくなる。政治家は綺麗事を言うのではなく、仕事をしてほしい。
通りすがり
集団移転が完了しても、たかだか25世帯のために病院、スーパー、銀行、郵便局は来ない、また生活に必要なトラブル時も、かけつけらる業者はなく、来ても出張費がかさみ生活コストは割高になる。もちろん25世帯のための公共交通手段も1日に2往復が良い程度だから、金沢などの避難先で安定して暮らせるなら、そちらを勧める。高齢者ならなおさらで、戻っても介護、病院に入る確率が高く自宅で過ごす時間は短い。故郷に対する思いは強いと思うが、現実をしっかりと受け止める必要がある。
hmu********
故郷や古巣への想いは誰にもわからないと思います。が、前を向いてほしい。移住先への不安もあるかと思いますが、プラス面もあります。年齢と共に住処の変化はストレスと言われます。それでも命を最優先に思案して頂きたい。大変な心労が重なり極限まできてるかと思いますが、どうか、雨風しのげ、少しでも快適に過ごせる環境をと願います
eri
被災することを考えれば集団移転もコミュニティの消失も致し方ないこと。たとえ公営住宅を設けても、以前の住まいよりもさらに高台になるか離れるかするだろうし、特に高齢者が多い地域では交通インフラが重要になってくる。住み慣れた土地を離れることもコミュニティ消失も寂しくはありますが、安定安心の生活を送るなら通院や買い物の便がいい場所に、という方がいい気がします。
hi_********
東日本大震災でも「この場所に戻りたい」と、嵩上げ工事を数年かかってしたにも関わらず、その土地には戻らずに土地は「虫食い」状態。特にその場に留まりたいのは高齢者世代で、土地に愛着もあり気持ちも理解するが、仮設住宅や公営住宅に移っている間に、年齢を重ね気持ちも変わり「戻りたいけど不便」や「子供の近くに住む」になってる現状がある。巨額な税金を投じてる以上「数年で気持ちが変わった」で良いのか?法的に強制的に移動させて、それでも残りたいのなら自分で整備して下さいにした方が良いかと思う。
gui*****
中途半端な移転よりも行政を中心に計画的な移転を大規模に実施すべ出来はないでしょうか?インフラの整備、維持にもお金がかかります。人口が大幅に減少するであることがわかっているのであれば、それなりの対応をしないと今後の生活事態を維持出来ない事が考えられます。
unw*****
介護の話になるけど、特に地方で田舎などに住む人を介護しようとしても1人済ませてから次の移動時間迄に相当な時間がかかって効率が悪くて只でさえ儲からないのにこうなると介護なんて出来ないだろうな。集団移転する方が理想的なのかもしれない。
新•国粋主義
誰も怖くて言わないが、日本の人口は年間90万人も激減しているのです。たった1年で和歌山県から人がいなくなった状況を意味します。この状況下で、湯水のごとく莫大な税金を投入して、震災前からひどく過疎っていた半島地域を元に戻す「復興」が必要なのでしょうか?賑わいが再び戻って来ないことは、東日本の復興事業で学習済みのはずです。半島過疎地の能登は街を元に戻す「復興」ではなく、大規模な農林水産業生産拠点や国立公園整備など、国家戦略としての国土のグランドデザインを議論すべきタイミングではないでしょうか?
cus********
ポツンと一軒家を見始めた頃は心の中でいいなー何て思っていましたが日本はこれから人口も減っていきます。被災地云々インフラが整っていない地域、密集地から離れた少人数の集落など集団移転を考えた方が良いと思います。一軒または数軒のために電気、水道、除雪、ごみ収集、道路保全諸々、大変になってくるのではないかと考えます。
mor********
移転される方達の地元愛もあるだろうが、年代もかなり高めで10年後にはかなり減ってるのではないかな。このような状況になってしまったら、自分の親なら先のことを考え、もう少し街中や足がなくても便利に住める所を勧めるかな。
2025年12月25日 集団移転で集落に明暗…能登各地に避難し意見集約できず断念、完成2年以上先「住民待ち続けられるか」
能登半島沿岸部の白丸地区では、津波と火災で約60軒が被災し、住民たちは海抜14メートルの高台への「集団移転」を決断。町は国の「防災集団移転促進事業」を活用し、2027年度完成を目指して災害公営住宅を建設する予定で、生活再建が進みつつあります。
一方、輪島市打越町では地震と豪雨で被災後、住民が各地に避難したため話し合いができず、集団移転計画を断念。区長も地区外に移り住み、「地域のつながり喪失」を懸念しています。
輪島市内の他の地区でも計画はありますが、土地確保や仮設住宅の退去が進まないなどの課題から、完成時期の見通しは立っていません。避難生活が長引くことで住民の意欲が低下し、コミュニティの崩壊や人口流出の懸念が広がっています。
要するに、被災地では「安全性」と「地域のつながり」の両立が難しく、行政手続きの遅れや高齢化もあって、移転先の整備が遅れるほどに住民が定住を諦めざるを得ない状況が生まれています。
この記事の深いテーマは「時間の経過が、被災地の再生意欲と共同体をどう変えていくか」です。