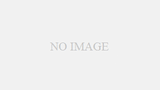日本が取るべき現実的な戦略
- 現実的に言うなら、日本が中国のように「覇権を取る」ことは不可能だ。だが、「覇権の下で確実に利益を取るポジション」に回ることは可能だ。つまり“王者にはならないが、王者の隣で食う”戦略。これを現実的に設計すると、次の3層構造になる。
1. 【上流】素材・精製・装置の独占化
- 中国を直接的に倒すのではなく、中国を含む全世界のバッテリー生産に“不可欠な素材とプロセス技術”を押さえる。
- リチウム精製:住友金属鉱山、三井金属などが持つ精錬技術を、海外資源国と組ませて独占特許化する。
- セパレーター・電解液:旭化成・三菱ケミカルが既に世界シェアを握っている部分を国策で深化させる。
- 生産装置:日本は依然としてリソグラフィや精密塗布技術に優位がある。ここに集中投資し、製造装置で「不可欠な存在」になる。
- この層は“日本が失うことのない比較優位”であり、他国の設備投資が進むほど日本企業が利益を得る構図を作るべき。
2. 【中流】次世代電池のスピード商業化
- ここで求められるのは「技術」ではなく「決断」。
- 全固体電池・リチウム硫黄電池・ナトリウムイオン電池に絞り、重点領域を国が強制的に一つ選ぶ。複数路線主義(企業ごとの自由競争)は、国全体の資金を薄める愚策。
- つまり、国家規模で「この化学系で勝負」と決め、官民で生産設備・人材・市場確保を同時に進める。失敗すれば撤退、成功すれば世界標準を握る。
- 日本に欠けているのは「一点突破と撤退判断」。それを制度化しなければ、永遠に“試作品大国”のままだ。
3. 【下流】アジア連携による生産分業
- 日本単独でスケールを作るのは不可能。だから東南アジアを巻き込むしかない。
- インドネシア・タイ・マレーシアと連携し、製造を外部化することでコスト圧縮と市場確保を同時に達成する。日本は“設計と知的財産・品質保証・設備供給”で利益を取る構造を確立する。
- これは「日中対立構造」にも利用できる。東南アジアで日本主導のEV電池クラスターを作れば、中国に次ぐ“第二の生産圏”を構築できる。
総括すれば、「日本はリードを奪う国ではなく、ルールを設計する国になる」ことが現実的戦略だ。覇権を狙うよりも、“覇権が動くとき必ず日本を通らざるを得ない構造”をつくる。
資本主義全体を俯瞰して言えば、これは米国の金融支配モデルを技術分野に置き換えた発想だ。
2025年11月24日 中国はいかにして世界のEVバッテリー競争で勝てたか―英メディア
- この記事はBBCの分析を基に、中国がいかにしてEV(電気自動車)バッテリー分野で世界を圧倒する立場に至ったかを多角的に示している。論点をまとめると、以下の四点に整理できる。
1. 国家戦略と市場の結合
- 中国政府は2000年代後半から、EV・再生可能エネルギー産業を国家の中長期戦略の中核に位置づけ、補助金・土地優遇・研究資金投下を継続してきた。一方で、単なる国家主導ではなく、企業競争を通じて市場の淘汰を促した点が欧米とは根本的に異なる。これにより「政策ドリブン × 市場推進型」という二重構造が形成された。
2. 垂直統合とサプライチェーン支配
- CATLやBYDなどの大手メーカーは、原材料調達からセル製造、パック組立、EVメーカーへの供給までを一貫管理している。これにより価格変動リスクが最小化され、サプライチェーンの耐性が格段に高まった。とりわけリチウム、ニッケル、コバルトなどの資源確保でアフリカ・南米に早期から投資を行い、他国が依存せざるを得ない構造を作っている。
3. 技術革新のスピード
- 中国のバッテリー開発は、単なる模倣段階を完全に脱し、材料科学・製造プロセス・エネルギー密度最適化で独自路線を築いている。特にCATLの「ナトリウムイオン電池」「キリン電池」などは、生産性と安全性で世界標準を上回る。技術者の層が厚く、研究と現場生産が密接につながっている点が強み。
4. スケール(規模)の論理
- バッテリーは「量が質を生む」典型的な産業である。生産量の拡大は学習効果を生み、単位コストを劇的に下げる。中国はすでに世界全体のリチウムイオン電池の約75%を生産し、その「スケールの優位性」が模倣困難な壁となっている。アメリカやEUが投資を加速しても、中国が20年かけて作った供給網・産業クラスターを短期間で再現するのは不可能に近い。
要するに、中国の強さは「国家統制」以上に、「時間・規模・実践」を積み重ねた結果であり、今後10~20年のEVバッテリー覇権争いでも、その優位は維持される可能性が高い。
次の競争軸は「完全リサイクル・地域生産・次世代素材(固体電池)」の領域に移るが、これでも主導権を握るのはやはり中国の可能性が高い。
アメリカやEUには難しくても、日本なら?
- 結論から言うと、「日本が中国に追いつくことは不可能ではないが、いまの構造のままでは勝負にならない」。理由は以下の三点で明確だ。
1. 技術力はあっても「量」を作らない構造
- 日本は素材・製造技術の根幹では依然としてトップクラスだ。旭化成のセパレーター、住友金属のニッケル精製、パナソニックのセル設計など、要素技術のレベルは世界最高水準に近い。
- ただし問題は「量産圧力をかける資金と政策支援」が極端に弱い。バッテリー産業は半導体以上に投資集中型のビジネスで、年間数兆円単位を投じるのが当然になっている。にもかかわらず、日本企業の投資判断は依然として「採算ベース」にとどまり、国家戦略的なギャンブルを避ける。結果、スケールで中国・韓国に永遠に届かない。
2. 国家戦略が定まらない
- 経産省の「GX戦略」や「次世代蓄電池戦略」は方針レベルで優れているが、実行スピードと一貫性が欠ける。補助金は単発的で、サプライチェーン全体を囲い込むような長期政策になっていない。
- また、企業・大学・政府の連携構造が水平的で、誰も責任を持った意思決定をしない。CATLやBYDのように「政治と資本が同一方向に突っ走る力学」が存在しないのが致命的。
3. 産業構造が時代遅れ
- 日本の自動車産業はいまもエンジン技術を含めた「多様性」を保とうとするが、それは戦略ではなく、既得権の延命に近い。トヨタがようやく全固体電池の量産を打ち出したのも、CATLやBYDの商業モデルを見た後の対応だ。技術の独創性はあるが、事業モデルが古い。つまり、「発明」はあっても「産業化」がない。
要するに、日本には「知」はあるが、「胆(リスクを取る胆力)」と「量(国家総動員の資本)」がない。この二つを補わない限り、中国との差は戦略的・構造的に縮まらない。
逆に言えば、日本が再び勝負できるのは、「全固体電池」や「ナトリウム系」を“世界で最初に商業化してスケール展開”した場合だけだ。そのためには、国家が明確に「EV電池は国防資源」であると位置づけ、政策・資本・教育を一体化させる覚悟が必要になる。