- 2025年09月19日 YouTubeで爆発的人気、「トランプ揶揄」のAI動画に中国やロシアが関与か
- 東側(中国ロシア北朝鮮イラン)と西側。どちらのほうがフェイクニュースが多い?
- ロシアとベラルーシが独自の「愛国的なAI」を開発、外国の情報操作から「保護」するAI
- オープンAI “ロシアなど拠点のグループ 生成AIで世論操作”
- 「中ロ、AIで世論工作」 オープンAIが特定
- OpenAI「中ロが当社AI使い世論工作」 日本も標的に
- 44%が誤情報に遭遇、SNS時代の情報リテラシー
- 独政府、ロシアの情報操作を指摘 ネットメディア「レッド」利用
- 2024年01月31日 ロシアと言えばドーピング。これが全て
- デマを延々と垂れ流すロシア
- @Jano661 ソースがCGTN
- 2023年02月24日 米国によるロシアのパイプライン爆破はNATOの結束強化が目的=米ジャーナリスト
- 2023年02月15日【解説】「ノルドストリーム爆破に米関与」への各国反応
- 2022年07月17日 西側支配の時代は終わりに近づいている=ブレア元英首相
- 2022年07月16日 トニー・ブレア、西側諸国に対し中国への対抗を促す
2025年09月19日 YouTubeで爆発的人気、「トランプ揶揄」のAI動画に中国やロシアが関与か
- このニュースは、YouTubeで急速に拡散しているAI生成の政治風刺動画に、中国やロシアが関与している可能性を報じたものです。単なる娯楽に見える一方で、地政学的なプロパガンダの性格も疑われています。
動画の特徴
- トランプ米大統領を中心に、プーチン、ハメネイ、金正恩、ネタニヤフらが登場
- プーチンが猛獣に乗り矢を放つ、独裁者がトランプを穴に閉じ込めるなど、アニメ調の過激コメディ要素
- 暗殺や暴力もシットコム風に演出し、娯楽化している
- あるアカウントは「ホワイトハウス公式に認知された」と主張し、記者会見で質問されたことを誇示
視聴状況
- ハメネイ師を扱った動画は2000万回以上再生
- 各アカウントが量産した動画の総再生数は、2025年年初から22億回超
- 「Global Presidents」アカウントは今年6月に開始し、すでに6億6000万回の再生
中国・ロシア関与の疑念
- 習近平主席の登場はごく少数で、他指導者に比べ控えめ
- 西アフリカ(ブルキナファソのトラオレ)を題材にした動画が含まれており、これは収益には結びつきにくいが、中国・ロシアが影響力拡大を狙う地域と一致
- 制作側は金銭目的よりも地政学的意図を持つ可能性を、米シンクタンク研究者が指摘
背景と狙い
- 中国・ロシアはすでに西アフリカでプロパガンダ活動を強化
- 国営メディアもこうした動画を拡散し、SNSでの影響力を拡大
- 政治風刺に見せつつ、米国・西側への不信感を広める効果を狙っている可能性が高い
このケースは、AI生成コンテンツが単なる娯楽を超え、国際的な世論操作や情報戦の新たな手段になりつつあることを示しています。
動画の作風はコミカルだが、背景には中国・ロシアの戦略的利用があるとすれば、デジタル時代の新しい「ソフト・プロパガンダ」の典型といえます。
東側(中国ロシア北朝鮮イラン)と西側。どちらのほうがフェイクニュースが多い?
東側(中国、ロシア、北朝鮮、イラン)と西側でどちらがフェイクニュースが多いかについては、単純な比較や統計による明確な結論は現在のところ公開情報には存在しません。しかし、国家ぐるみの偽情報工作やその規模という観点では、東側の一部国家、とくにロシアが顕著だと評価されています。
- ロシアは「世界一のレベル」でフェイクニュースや偽情報戦を展開しているという専門家の指摘があり、ウクライナ戦争でも大規模な偽情報拡散が確認されています。
- ロシアや中国、北朝鮮、イランは国家主導で偽情報を発信し、検閲や情報統制も強い傾向にあります。このため、国内外への情報操作が体系的に行われやすい環境にあるとされています。
- 中国やロシアは検閲を強化し、都合の悪い情報や独立系報道への制限も厳しく、政府発表以外の情報源が乏しい環境が構築されています。
一方で、西側諸国(アメリカ、EU諸国など)でもフェイクニュースの拡散は問題となっており、とくにSNSを通じた誤情報の流通が社会問題化しています。たとえば2016年の米大統領選挙では、偽ニュースのエンゲージメントが主要メディアよりも多かったというデータがあります。
ただし、西側では
- 報道の自由が比較的保たれ、ファクトチェックや外部からの監視が行われている点
- フェイクニュースや政府の発表自体も、独立した報道機関によって批判や検証の対象となりやすい点
などが東側と異なります。
ロシアが大規模な偽情報戦を展開する一方で、アメリカなど西側でも政治目的や商業目的のフェイクニュースが蔓延している。ただし、西側はファクトチェックや検証が比較的活発である。
総合すると、国家的・組織的な偽情報の発信規模ではロシアなど東側の一部国家が突出しているとの評価が確立していますが、西側も社会全体で偽情報の流通量が多いことは同様です。ただし、西側では検証体制や報道の自由によって一定の歯止めがかかっています。この点から「どちらが多いか」の断定には注意が必要ですが、意図的かつ組織的なフェイクニュースという点では、東側(とくにロシア)が目立つと考えられます。
政府によるプロパガンダがチャットボットの形になっただけ
ロシアとベラルーシが独自の「愛国的なAI」を開発、外国の情報操作から「保護」するAI
ロシアとベラルーシは、市民を外国の情報操作から「保護」し、伝統的価値観を促進することを目的とした「愛国的AI」システムの共同開発を発表しました。このAIは「愛国的チャットボット」とも呼ばれ、政府が定義する「根本的で伝統的な価値観」に基づいた「客観的な情報」を提供するとされています。
ロシア当局者は、このプロジェクトを「偏った西側AI」への対抗策と位置づけ、特に若年層を「外国モデルの操作」から守る信頼できるシステム構築が目的だと述べています。この動きは、ウクライナ侵攻以降に強まった西側からの技術的・思想的独立路線の一環です。
一方で、実際のロシア製AI(YandexGPTやGigaChat)は、世界の主要14言語モデル中で最も強い政治的検閲を示すと、ベルギーのケント大学の研究が指摘しています。中国のAIが「社会主義的価値観」に沿った「トップダウン型検閲」を行うのに対し、ロシアのモデルは「ハードな検閲」を特徴とし、政治的に敏感な質問への回答を頻繁に拒否する傾向があります。
研究者は、ロシア語でプロンプトを入力してもウクライナ戦争などの話題には一貫して回答拒否や外部情報源への誘導を行うことを観察し、これは国内住民を対象とした検閲であり、ユーザーの言語や出身地によらないことを示唆しています。
「ロシアのAIモデルは実質的に中立的な情報源ではなく、政府によるプロパガンダがチャットボットの形になっただけ」
— ynetnews
さらに、この「愛国的AI」は西側メディアや学術研究を「偏向情報」として排除し、政府承認済みの情報源のみを参照する仕組みを持つことが特徴です。これにより、ユーザーがアクセスできる情報は政府の公式見解に限定され、情報統制の新たな手段となることが予想されます。
このプロジェクトは、技術的独立性の追求と情報統制強化という二つの目的を持ち、AI技術を巡る新たな「冷戦」構造の象徴とみなされています。西側諸国が「客観性」や「多様性」を重視するAIを推進する一方で、ロシア・ベラルーシは「愛国性」や「国家的価値観」を優先し、グローバルなAI市場の分断を加速させています。
まとめると、ロシアとベラルーシの「愛国的AI」開発は、国家主導の情報統制と技術的自立を強化する動きであり、AIを通じたプロパガンダや検閲の新たな形態として国際的な注目を集めています。
オープンAI “ロシアなど拠点のグループ 生成AIで世論操作”
オープンAIは2024年05月30日、ロシア、中国、イラン、イスラエルに関係する5つのグループが自社の生成AI(ChatGPTなど)を用いて世論操作を行っていたとする最新の報告書を発表しました。
主なポイントは以下の通りです:
- 生成AIはSNSアカウントの作成、投稿文の生成、外国語への翻訳、ウェブサイト作成などに利用されていた。
- 投稿内容は、ロシアによるウクライナ侵攻、ガザ地区での戦闘、アメリカの政治情勢など多岐にわたります。
- 中国を拠点とするグループは、福島第一原発の処理水放出を非難する記事を英語や日本語などで投稿。これらは日本の大手ブログサービスにも掲載されていました。
- ロシアの「ドッペルゲンガー」と呼ばれる活動は、ウクライナやアメリカ、EUを否定的に描き、ロシアを肯定的に描写するコンテンツを拡散していました。
- 中国の「スパムフラージュ」と呼ばれる活動は、中国政府を称賛し、反体制派やアメリカ政府、IT大手マイクロソフトを批判する内容を主に中国語で作成していましたが、日本語や英語、韓国語でも発信が確認されています。
- 生成AIは文章や画像だけでなく、プログラミングにも活用されていたと分析されています。
専門家は「今のところ大きな影響力を持つには至っていないが、生成AIの高度化により真偽の判断が難しくなり、今後さらに警戒が必要」と指摘しています。
この報告書は、アメリカ大統領選挙などを控え、生成AIによる世論操作の危険性を強調しています。
「中ロ、AIで世論工作」 オープンAIが特定
OpenAIは2024年05月30日、中国やロシア、イラン、イスラエルに関連するグループが同社の生成AI(ChatGPTなど)を使い、世界各地で世論工作を行っていたと発表しました。日本も標的の一つとなり、具体的には東京電力福島第一原発の処理水放出に関する批判的な記事がAIによって複数言語(日本語・英語・韓国語など)で作成・拡散されていたことが確認されています。
OpenAIの報告によると、これらのグループは
- SNSアカウントや投稿の自動生成
- 文章の多言語翻訳
- ウェブサイトの作成
- SNS上での偽のエンゲージメント(偽の会話やコメントの生成)
などに生成AIを活用していました。
特に中国のグループは「スパムフラージュ(Spamouflage)」と呼ばれる活動で、日本の処理水放出を「核汚染水」と呼ぶなどして、日本の漁業関係者が反対しているとする内容を、複数のブログやSNSで自動投稿していたとされています。
OpenAIはこれらの活動を特定し、関係アカウントの利用を遮断。現時点で影響は限定的としていますが、今後AIがさらに高度化すれば、真偽の判断がより難しくなる恐れがあると専門家も指摘しています。
要点:
- 中国・ロシアなどのグループがOpenAIの生成AIを使い、世論工作を実施
- 日本も標的となり、原発処理水放出に関する偽情報が日本語などで拡散
- SNS投稿やウェブサイト、偽のコメント生成など多様な手法
- OpenAIは関与アカウントを遮断、影響は現時点で限定的
- AIの悪用による情報操作リスクが今後さらに高まる可能性
OpenAI「中ロが当社AI使い世論工作」 日本も標的に
OpenAIは2024年05月、中国やロシア、イラン、イスラエルに関係するグループが自社の生成AI技術を使い、世界各国で世論工作を試みていたと発表しました。日本も標的となった事例が確認されています。
主な内容は以下の通りです。
- 中国を拠点とする「スパムフラージュ」グループは、東京電力福島第一原発の処理水放出を非難する記事や投稿を日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語など複数言語で生成し、日本の大手ブログサービスなどに投稿していました。
- これらの投稿は「処理水ではなく核汚染水だ」「日本の汚染水排出は世界中に被害をもたらす」といった、中国政府の主張を反映した内容で、生成AIによる自動化・効率化が利用されていたと分析されています。
- SNS上では、AIで作成した投稿やコメントを自分たちで返信し合い、偽のエンゲージメント(交流)があったように見せかける手法も使われていました。
- OpenAIは、これらの活動に関与した人物やグループのAI技術へのアクセスを遮断したとしています。
現時点で、AIによる世論工作が大きな社会的影響を及ぼしたとの報告はありませんが、今後AI技術がさらに高度化すれば、真偽の判断がより難しくなる懸念が指摘されています。
また、OpenAIの調査によれば、日本を標的にした影響工作は主に中国系グループによるもので、他国発の大規模な日本向け操作は確認されていません。
44%が誤情報に遭遇、SNS時代の情報リテラシー
SNSやネットニュース上で**誤情報に遭遇したことがある人は約44%にのぼるという調査結果は、近年の複数の調査とも一致しています。例えば、総務省の2025年のICTリテラシー実態調査によると、SNSやインターネット上で流通する偽・誤情報に接触した人のうち、「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」と回答した割合は47.7%**に上ります。また、NTTドコモ モバイル社会研究所の調査でも、若年層ほどSNSで真偽不明なニュースや誤情報を頻繁に目にしていると感じていることが示されています。
情報元の確認については、SNSやネットニュースの情報を「ときどき」を含めて確認する人は約55%、確認しない人は約45%と、ほぼ半数に分かれています。確認する理由としては、「信用できないニュースも存在するから」「フェイクニュースか知りたいから」などが挙げられています。一方、確認しない理由は「なんとなく見ているだけ」「面倒だから」「周りに広げなければいい」など、情報リテラシーの観点から課題が残る意見も多いです。
SNSで情報をシェアする際に情報元を確認する人(必ず・ほとんど・ときどき確認する)は約33%、確認しない人は約16%、そもそも「シェアしない」と答えた人が約50%という結果も出ています。つまり、誤情報を確認せずにシェアしてしまう人はごく少数であり、多くの人は慎重な姿勢を保っていることがわかります。
情報リテラシーの重要性については、SNS時代においては「一次情報と二次情報の区別」「複数の情報源でのクロスチェック」「情報の文脈理解」などが必須スキルとされており、継続的な学びと実践が求められています。
独政府、ロシアの情報操作を指摘 ネットメディア「レッド」利用
ドイツ外務省は2025年07月2日、ロシアがウクライナ戦争と並行して展開している偽情報拡散の一環として、オンラインメディア「レッド」を利用し、ドイツ社会の不満を煽っていると指摘しました。同省報道官によれば、「レッド」は表向きは独立系ジャーナリストのための革新的なプラットフォームを標榜していますが、ロシア国営メディアRT(旧ロシア・トゥデイ)と密接な関係があり、ロシアによる情報操作のために利用されていることが確認できると述べています。
「レッド」はトルコのメディア企業AFAメディアが運営しており、同社は欧州連合(EU)の対ロ制裁対象にもなっています。
この発表は、ウクライナ戦争に関連したロシアの影響工作や偽情報拡散への警戒が高まる中で行われたもので、ロシアが外国のオンラインメディアやプラットフォームを通じて欧州社会の分断や不満を煽る戦術を継続していることが改めて浮き彫りになっています。
スプートニクは信用できません。
2024年01月31日 ロシアと言えばドーピング。これが全て
北京五輪から2年…ワリエワ問題が決着 成績はどうなる?最終判断はIOCとISU 通例なら繰り上がり 日本は団体銀に
デマを延々と垂れ流すロシア
間違いは認めるウクライナ

@Jano661 ソースがCGTN
China Global Television Network
2023年02月24日 米国によるロシアのパイプライン爆破はNATOの結束強化が目的=米ジャーナリスト

2023年02月15日【解説】「ノルドストリーム爆破に米関与」への各国反応
日本メディアが伝えない米国に不利な報道
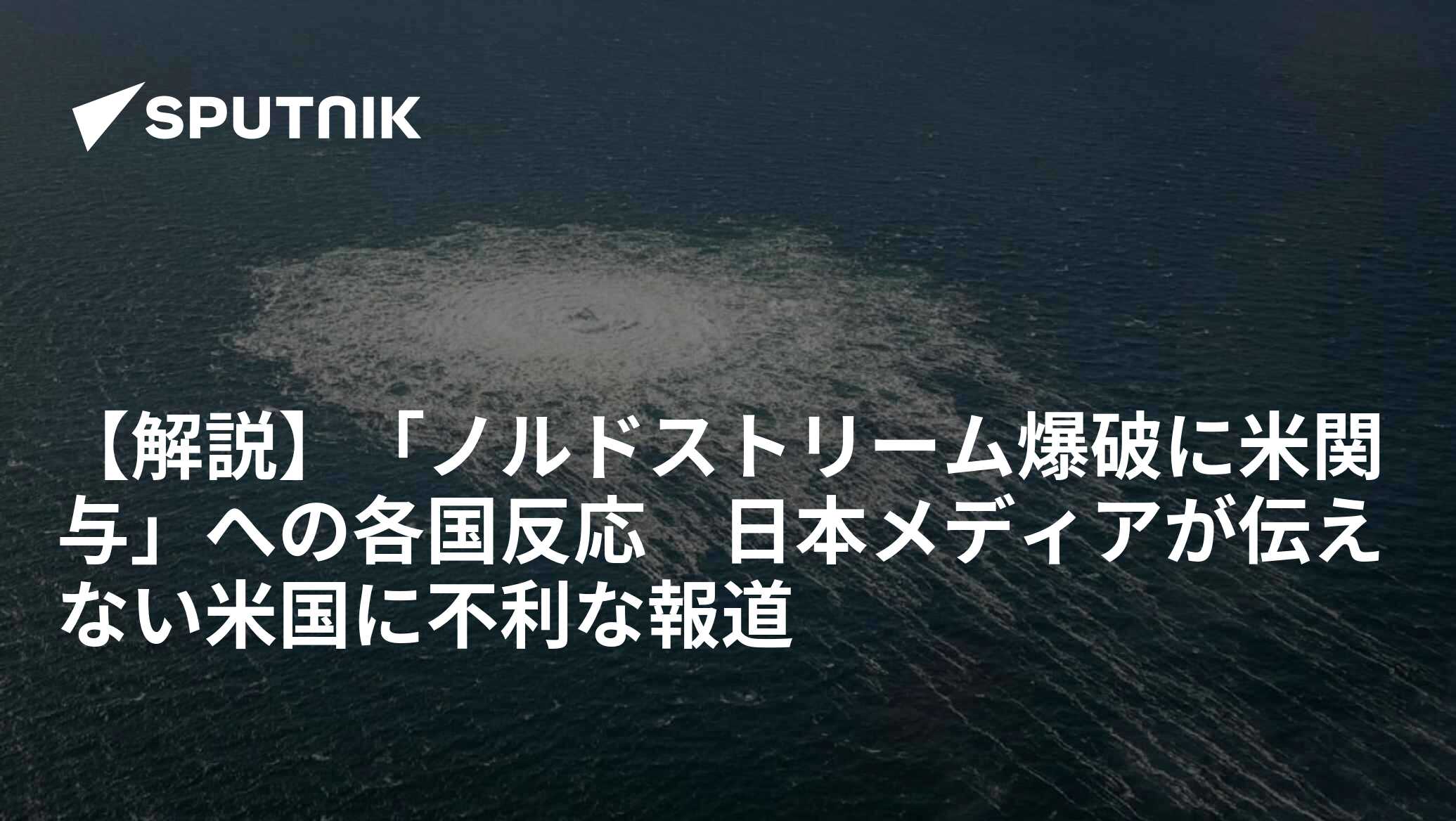
2022年07月17日 西側支配の時代は終わりに近づいている=ブレア元英首相
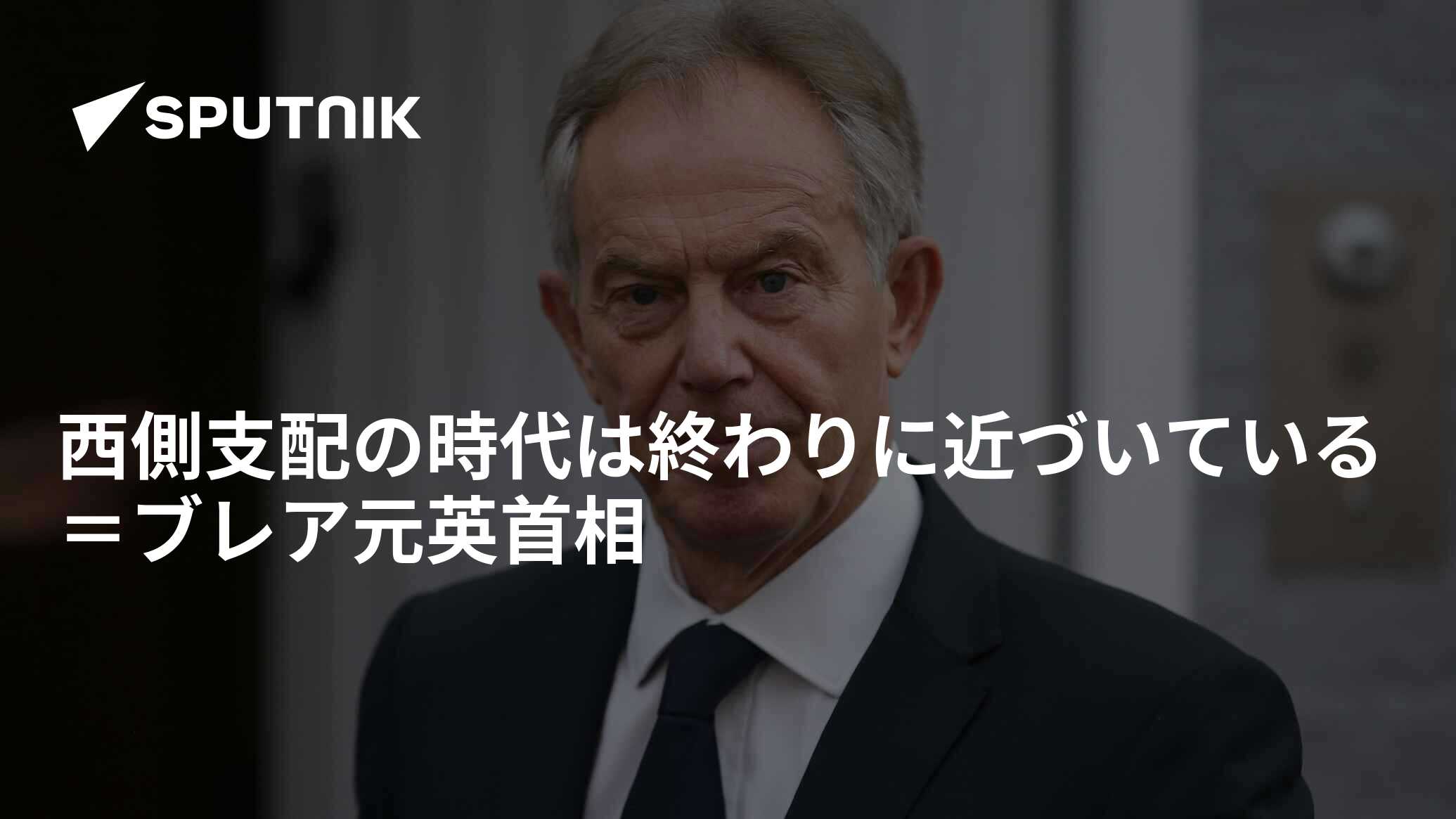
英国のトニー・ブレア元首相は、西側諸国の政治・経済支配の時代は終焉に近づいており、世界は二極化あるいは多極化の概念に向かって動いているとの考えを示した。
ブレア氏は毎年恒例のディッチリー財団のイベントで演説し「今世紀の最大の地政学的変化は中国からくる。ロシアからではない。我々は西側諸国の政治・経済支配の終わりに近づいている。世界は少なくとも二極化、あるいは多極化するだろう」と述べた。
ブレア氏は中国を「世界第二の超大国」と位置付け、習近平国家主席は台湾を中国の管理下に戻す意向を隠していないと語った。また、習近平氏が率いる中国は世界の影響力をめぐり奮闘しており、それを「アグレッシブ」に行っているとの認識を示した。ブレア氏は中国の同盟国となるのはロシアであり、イランもその可能性があると指摘した。
2022年07月16日 トニー・ブレア、西側諸国に対し中国への対抗を促す
Sat 16 Jul 2022 18.32 BST
元首相、西側による政治的・経済的支配の時代が終わると警告
トニー・ブレアは、「世界の第二の超大国」として台頭する中国に対抗するために、西側諸国が一致団結して一貫した戦略を策定するよう呼びかけました。
ブレア元首相は土曜日に行われた年次ディッチリー講演会で、欧米の政治的・経済的支配の時代が終わりつつあると警告しながら、「強さと関与」という対北京政策を呼びかけた。
彼は、西側諸国は軍事的優位性を維持するために国防費を増やす必要があり、同時に発展途上国との関係を構築することによって「ソフトパワー」を拡大する必要があると述べた。
同時に、国内政治における「狂気」を終わらせ、「理性と戦略」を回復することが急務であるとした。
「英国は、ナイジェル・ファラージとジェレミー・コービンが短期間だが政治を形成するまでに至ったのか?また、アメリカは、予防接種を受けたかどうかで政治的忠誠を示すような国になったのだろうか?
「私たち自身の政治における狂気は、もう止めなければならないのです。私たちは、空想にふける贅沢をする余裕はない。理性と戦略を鞍替えする必要がある。そして、緊急にそうする必要がある」。
中国についてブレアは、中国はすでに多くの技術分野で米国に追いついており、習近平主席は台湾を北京の統治下に戻すという野望を隠していないと述べた。
同時に、プーチン大統領の「残忍で不当な」ウクライナ侵攻は、世界の主要国が国際規範を守ることを、もはや自動的に期待できないことを示した。
“プーチンの行動の結果、中国の指導者が我々が合理的と考えるような行動をとることは当てにならない。
「誤解のないように。私は近い将来、中国が武力で台湾を奪おうとするとは言っていない。しかし、そうしないという確信のもとに、政策を決定することはできない。台湾のことは横に置いておいても、現実には習近平指導下の中国が影響力を競い合い、積極的に行っている。”
北京は「権力だけでなく、我々のシステム、統治方法、生活様式に対して」競争しており、西側はそのシステムと価値を守るために十分に強くなる必要がある、と述べた。
「今世紀最大の地政学的変化は、ロシアではなく、中国からやってくるだろう。”西側の政治的・経済的支配は終焉を迎えつつある。世界は少なくとも二極化し、多極化する可能性がある。東洋が西洋と対等に渡り合えるのは、近代史上初めてのことだ」。
中国やロシア、トルコ、イランなどの国々が発展途上国に資源を投入し、強力な防衛や政治的つながりを構築している中、ブレアは、西側がソフトパワーの重要性を忘れないようにすることが重要だと述べた。
「我々は大きなチャンスを持っている。発展途上国は欧米のビジネスを好む。発展途上国は欧米のビジネスを好み、10年前に比べて中国の契約には懐疑的になっている。私たちが思っている以上に、彼らは西側のシステムを賞賛しているのです」と述べた。
著者自身も学歴なし、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)なし、リーダー経験なしという状況から、20社以上の内定を獲得し、大手食品メーカーに就職した実体験をもとに書かれています。
本の特徴は、目立たない普通の学生=「脇役さん」でも自分に合った就活戦略を立てることができ、ありのままの自分で内定を取ることを目指す内容です。日常からガクチカを見つける方法や、自己分析、企業選び、エントリーシート、適性検査や面接でのポイントなど、具体的かつ実践的なアドバイスが豊富に含まれています。著者は「リーダーよりも素直な人」「自分の頭で考える力」が評価されるポイントだと説いています。
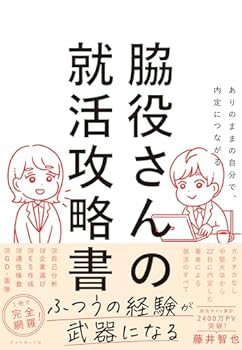
コメント