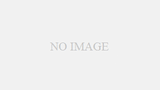2025年11月24日 習近平氏は「タイムリミットがあるので焦っている」”強硬指示”の背景を元朝日新聞記者が解説
- この記事の本質は、中国の外交強硬化の「なぜ今なのか」という点にある。峯村健司氏(元朝日新聞記者、キヤノン戦略研究所上席研究員)は、単なる外交的反発ではなく、習近平の個人的・政治的焦りが背景にあると分析している。
習近平の焦りの構造
- 峯村氏は、習近平の任期が2028年に迫る中で「台湾統一」という政治的・歴史的ミッションを完遂したいという強迫観念のような焦りが生じていると見る。
- 習は一度延長した任期をさらに正当化するには「成果」が必要であり、その最重要課題が「台湾統一」。つまりこれは単なる外交目標ではなく、習政権の「自己正当化プロジェクト」でもある。
- そのため、台湾問題に関与する日本の動きを「自らの歴史的達成の妨害」と捉え、強硬な対抗措置(日本産海産物の輸入停止、渡航自粛など)を命じたという構図が見える。
峰村氏の分析の意味するもの
- 中国の行動は段階的エスカレーション型。
すぐに最大圧力をかけるのではなく、反発を計測しつつ徐々に強度を上げてくる。これは外交的「威嚇」と「実力行使」の中間領域を意図的に操る戦略。 - 強硬姿勢は“下からの圧力”ではなく上からの指示。
官僚機構や地方政府が暴走しているのではなく、習本人の「政治的指令」としての硬直化。個人支配的構造が国家の政策柔軟性を奪っている。 - 2024~2027年は最も危険な時期。
台湾総統選、米国大統領選、そして習近平の次期政権計画が交錯する。習にとっては「後がない4年」になる。
日本に対しては軍事的行動ではなく、「心理的・経済的圧力」(国内世論の分断、経済報復、サイバー攻撃など)で揺さぶる戦略に出る可能性が高い。
要するに
- 中国の日本への強硬姿勢は、習近平の焦燥と時間制約が直結している。外交戦略というより「政治的焦りの外在化」。
- 今の中国は、理性的な国益よりも体制維持と「歴史的達成」の演出を優先している。そのため、論理的な対話ではなく、象徴的対抗行動(経済報復や世論戦)が増える。
この動きを読むべき視点は、「外交」ではなく「習政権の延命戦略」として見ることだ。日本政府がそれに反応的対応を続けるなら、完全に相手のペースに嵌まる。冷静さと持久戦的対応こそが、日本がすべき「最強の反撃」になる。
日本は「台湾有事は日本有事」問題にどう対処すべき?
- この問題は「政治声明」ではなく「戦略命題」として考える必要がある。なぜなら「台湾有事=日本有事」は単なるスローガンではなく、実際にどの程度日本が巻き込まれるか、どの範囲で行動するかという冷徹な現実判断を問う命題だからだ。
日本が直面している現実構造
- 地理的不可避性
台湾海峡から与那国、石垣、那覇まではわずか数百キロ。米軍の展開、航路の遮断、通信・衛星妨害、難民流入などいずれにおいても日本は後方支援地ではなく「前線の一部」となる。 - 日米同盟の義務関係
台湾防衛そのものは同盟条約の対象外だが、米軍施設や補給網は日本国内に集中している。すなわちアメリカが台湾支援行動に入れば日本も自動的に「基地提供・兵站・支援」の形で関与せざるを得ない。 - 経済・情報リスクの広がり
有事にならずとも、中国が報復的に日本を経済制裁(輸出制限、旅行制限、通信・金融圧力)対象にする可能性が極めて高い。軍事より先に「経済有事」から始まる。
対応の柱
- 政治的に静かに準備し、騒がず動く。
日本の最大の失敗は「言葉で強気、実務で空洞」になりやすいこと。外交的挑発や勇ましい発言よりも、機能する避難計画、通信インフラ防衛、輸入代替策の整備など地に足の着いた備えに重心を置くべき。 - 抑止効果を実体で示す。
自衛隊の統合作戦力・長射程ミサイル配備・衛星通信防護など、実際に「攻められないコスト」を積む。発言や法理論では抑止にならない。 - 中国との“限定的直通対話”を保つ。
全面対立を煽る国会答弁や首相発言は習近平の「外敵を必要とする政治心理」に利用されるだけ。むしろ危機管理チャンネル(ホットライン・工作レベル協議)を裏で維持すべきだ。 - 日米台の「非軍事安全保障連携」を拡充。
例えばサイバー防衛、インフラ防護、情報共有、物資備蓄。軍事的衝突を前提にせず、“有事前段階”への備えを同盟行動として制度化する。 - 発想を変えるべき点
「台湾有事」そのものを防ぐことが最上の安全保障。
つまり「有事後対応」ではなく「有事を起こさせない政治・経済・心理的設計」を優先すべきだ。東京が取るべきは“参戦の準備”ではなく、“戦争回避の設計”。
現状の政治発言(台湾有事=日本有事)は、抑止効果よりも国内政治アピールとして機能している面が強い。真に必要なのは勇ましさではなく、冷静で地に足のついた国家設計だ。
日本がこれから問われるのは、「戦う準備をどう整えるか」ではなく、「戦わなくて済む構造をどう作るか」である。