2025年12月21日 衆院定数、次期選挙は削減困難 自民選対委員長が見通し
この記事は、自民党の古屋圭司選対委員長が21日に岐阜県中津川市で講演し、衆議院議員の定数削減が次回の衆院選には間に合わないとの見通しを示したという内容です。
古屋氏は、仮に来年(2026年)の通常国会で定数削減法案が成立しても、与野党協議や選挙区の区割り改定に時間がかかり、「適用は任期満了の2028年秋ごろまでかかる」と説明しました。そのため、もしそれ以前に衆院が解散された場合は「現行制度で実施することになる」と述べ、次期選挙への適用は「正直言って厳しい」としています。
また、衆院解散の時期については、高市早苗首相が掲げる政策への「思い入れが強く」、通常国会で成果を積み上げた上で「国民から評価を得た最も良いタイミングで解散に踏み切るだろう」との見方を示しました。
要するに、定数削減の実施は次回総選挙(高市政権下での解散)には間に合わず、当面は現行制度のまま選挙が行われる可能性が高い、ということです。
反対をしているのはどの政党?
衆院定数削減法案に反対の立場を示している主な政党は、日本共産党、立憲民主党、国民民主党、公明党、れいわ新選組、有志の会です。
これらの野党6党・会派は12月8日に会談し、自民党と日本維新の会が提出した法案を「受け入れられない」との認識で一致しました。 日本共産党は特に「多様な民意を削るもので行政監視機能が後退する」と強く主張しています。
一方、自民党と日本維新の会は連立合意に基づき推進しており、他の政党は慎重論を展開しています。

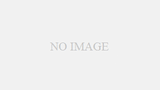
コメント