関連動画 Goats eating backyard over 6 days
関連動画 Goat Infestation – Cephalonia 2007
牧畜・放牧によって森林が失われ表土が流出してしまった
もともとは、ギリシャ半島も緑に覆われ、それなりの地味もあったという意見もあります。
主として牧畜、羊の放牧によって森林が失われ、表土が流出してしまったのだという推測です。
- ペリクレスのころまではまだ森林は大丈夫だったようですね。史料では艦隊を作るのにも人手と財源の確保が主たる関心事だったみたいだし、当時のおかずが海産物が主だったことを考えると。ペロポネソス戦争後(ソクラテスの頃)にはどうだったんだろう?
- 農地の荒廃は、造船用木材の濫費と商品作物のオリーブ・葡萄の連作が原因だったらしい。テレビ朝日 5月18日 23:30-24:00 素敵な宇宙船地球号「神々の大地を守る~ギリシャ 粘土だんごの実力」
- そのテレビ番組を見ていないので良くわからないのだが、農地の荒廃の原因として「造船用木材の濫費」はともかく、「オリーブ・葡萄の連作」というのはどういう意味なんだろう?言うまでもなくオリーブや葡萄は多年生植物で荒れ地でもよく育つが、前者は植えてから30-50年、後者はそこまではいかないものの、これもかなりの年月が経たないと安定した収穫が出来ない性質を持つ。そのかわりオリーブなど木の寿命は数百年にも及ぶし、葡萄だって寿命は長い。要するに両者とも極めて大器晩成型の果樹なのだ。はっきり言ってアルカイック期・古典期のギリシャよりずっと寿命が長いわけで「連作」もなにもあったもんじゃないと思うのだが。
- むしろ山羊とか羊によって林業が盛んになるまえに、樹の芽が摘まれちまったのがでかいとおもう。羊と山羊は確かに荒地でも一定の草があれば育つ。だが注意しないと、せっかく発芽した木の芽も食べてしまう。また樹が育たないとなると、そもそも輸入ができなくなってしまう。船が作ることができないからね。この場合ではオリーブと葡萄しか作ることができないという意味じゃないのかな?船を作るとなると別の樹が必要だとおもうから。
放っておくと何でも食べてしまい森林破壊、環境破壊のもとになる
まあ、実際に番組を見てないんだからどうのこうの言っても仕方がないね(苦笑)。確かに山羊や羊の導入は文明にとってリスク要因なのだと思う。消化器の能力もあるのだろうが、羊は口唇部の解剖学的構造により短い草でも根本からたべることが出来るし、山羊は殆どどんな場所にも移動でき、粗剛な茎や葉をも食べることができるため、放っておくと何でも食べてしまい森林破壊、環境破壊のもとになる。たしかカスティリヤの環境破壊も羊や山羊の大規模な移牧が原因の一つだったはずである。ただ、農学者岩片磯雄が「古代ギリシャの農業と経済」(大明堂)で書いていることを少しアレンジして言うと、畑作には家畜由来の厩肥が必要だし羊や山羊は粗悪な飼料でも育ちうるというメリットはあるわけで、環境に対して無配慮な放牧、移牧にさえ注意すれば、即ち大切な樹木の若芽を食べさせてしまったり、あるいは畑に還元すべき糞をそれ以外の場所にばらまいてしまうことさえなければ森林、畑、牧畜という三者のバランスも取りえたらしい。要するに山羊も羊も飼い方次第だったのだろう。それと当時においても、特にアッティカの環境破壊が顕著だったのは陶器の製造のため燃料として大量に木材を伐採したことも原因だったそうだ。これは景徳鎮と同じだね。
- 土壌が流出して良好な港湾が埋まったために貿易能力が低下。さらに湿地になりマラリアが流行して人口が減少。ってこともギリシャが衰退した原因でないかと。多くの文明衰退の原因が森林伐採後の土壌流出による様様な影響をうけてますね。南アメリカは除くけど(笑)
古代ギリシャ文明と森林資源 環境への取り組み -丸紅-
オリンピックの起源
- 今年は4年に一度のオリンピックイヤーです。8月13日から29日までの17日間にわたり、ギリシャの首都・アテネにおいて、各競技の熱戦が繰り広げられます。1896年以来、108年ぶりにアテネで開催される近代オリンピックですが、そもそもオリンピックの起源は古代ギリシャにまでさかのぼり、日本がまだ縄文時代だった紀元前776年に、ギリシャのオリンピュアという地で始まりました。当時は、各ポリス(都市国家)から、えり抜きのアスリートたちが集まり、ポリスと個人の威信と名誉をかけて死闘を繰り返した、と言われています。
- 全盛期には約1,500ものポリスが存在し、隆盛を極めた古代ギリシャですが、その後、文明は衰退し、遺跡が当時の面影を伝えるだけです。 ではどうして古代ギリシャ文明は衰退してしまったのでしょうか? その原因は、実は環境問題と深いつながりがあるのです。
環境問題に対する「哲学」の欠如
- 紀元前1500年ごろ、ギリシャはまだ豊かな森林資源を有していたと推測されています。当時の人々は、この森林資源を最大限に活用していました。 当時の地中海文明は、交易や商業によって支えられていた面が強いのですが、地中海周辺は山がちだったため、輸送手段は海上輸送に頼っていました。そのためたくさんの船が必要になり、船を作るための木材が必要になりました。 また日々の食事においても同様で、パンを焼くにも、肉や魚を調理するにも燃料として木が使われました。
- さらに、土器、陶器や、戦闘に必要な武器・よろいの製造などにも、木材は不可欠でした。このように、古代ギリシャにおいて木材は、ほとんどの経済活動のための資源・エネルギー源として用いられており、まさに木に依存して生活していたと言えます。木材利用をベースに経済が発展するに伴い、人口が増加し、さらにたくさんの木材が必要になって森林伐採が加速され、土壌浸食や砂漠化が進みました。 そして、次第に増加した人口を支えるだけの森林資源を確保できなくなり、ギリシャの覇権は、森林資源を有していた北方のマケドニアへ移っていったのです。
- 当時は「持続可能な発展」という「哲学」はなく、経済発展のことだけを考えて森林を伐採していった結果、文明の基盤そのものが失われ、古代ギリシャは滅亡したと言えます。 メソポタミヤやローマなど、ほかの古代文明の滅亡についても、森林資源の枯渇が、その一因になったと考えられています。 このように、人類は有史以来、自然の恵みを利用することで、環境に負荷を与えつつ、文明社会を形成してきました。しかし、その負荷が一定の限度を超えると、自然環境のバランスが崩れてしまい、私たちの生存基盤をも脅かすことになりかねません。私たちも、古代文明の盛衰の歴史から学ぶべきことがあるかもしれません。
ヤギによる耕作放棄地管理と「第3の選択肢」
背景と課題
- 耕作放棄地の所有者は、「再び活用する」か「完全に放置する」かという二択に悩まされ、精神的・経済的な負担を抱えています。放置すれば雑草繁茂や景観悪化、獣害リスクなどの問題が発生し、管理には人手やコストがかかります。
株式会社むじょうの「第3の選択肢」
- 株式会社むじょうが提案するのは、耕作放棄地を「活用」でも「放置」でもなく、ヤギを使って“ゆるやかに維持”する「粗放管理」という第三の選択肢です。
「草刈りヤギちゃん」サービスの特徴
- ヤギをレンタルし、機械や除草剤を使わずに自然な雑草管理を実現。
- 急斜面や機械が入りにくい場所でも対応可能。
- 除草剤を使わないため土壌や生態系への負荷が少なく、CO₂排出もありません。
- ヤギが草を食べるので刈り取った草の処分が不要。
- かわいらしいヤギの存在が地域住民の癒しやコミュニティ形成にも寄与。
「縮充」という新しい土地利用モデル
- むじょうは、人口減少社会において「無理に守らない」「適切な規模に畳む」「余白を活かす」といった考え方で、土地との新しい関係性を提案しています。ヤギによる粗放管理は、土地の可能性を維持しつつ、所有者や地域の心理的負担を軽減し、将来的な農地再利用や自然再生の選択肢も残せる方法です。
社会的意義と今後の展望
- コスト削減・作業負担軽減・景観維持・獣害リスク低減など多面的な効果。
- 地域のコミュニティ拠点としての役割や、教育・観光資源としても期待されています。
- 今後は、自治体や企業との連携を広げ、粗放的な管理手法の普及と社会的意義の検証を進めていく方針です。
- 「耕すか、放棄するかという二択しかなかった時代は、もう終わりにしなければなりません。むじょうは、耕さないけれど手放さないという第三の選択肢――粗放管理という形を提示し、農地の未来を柔らかく支える仕組みをつくっていきます。」
- ヤギによる耕作放棄地の粗放管理は、土地と人が無理なく心地よくつながり続けるための新たなモデルとして注目されています。
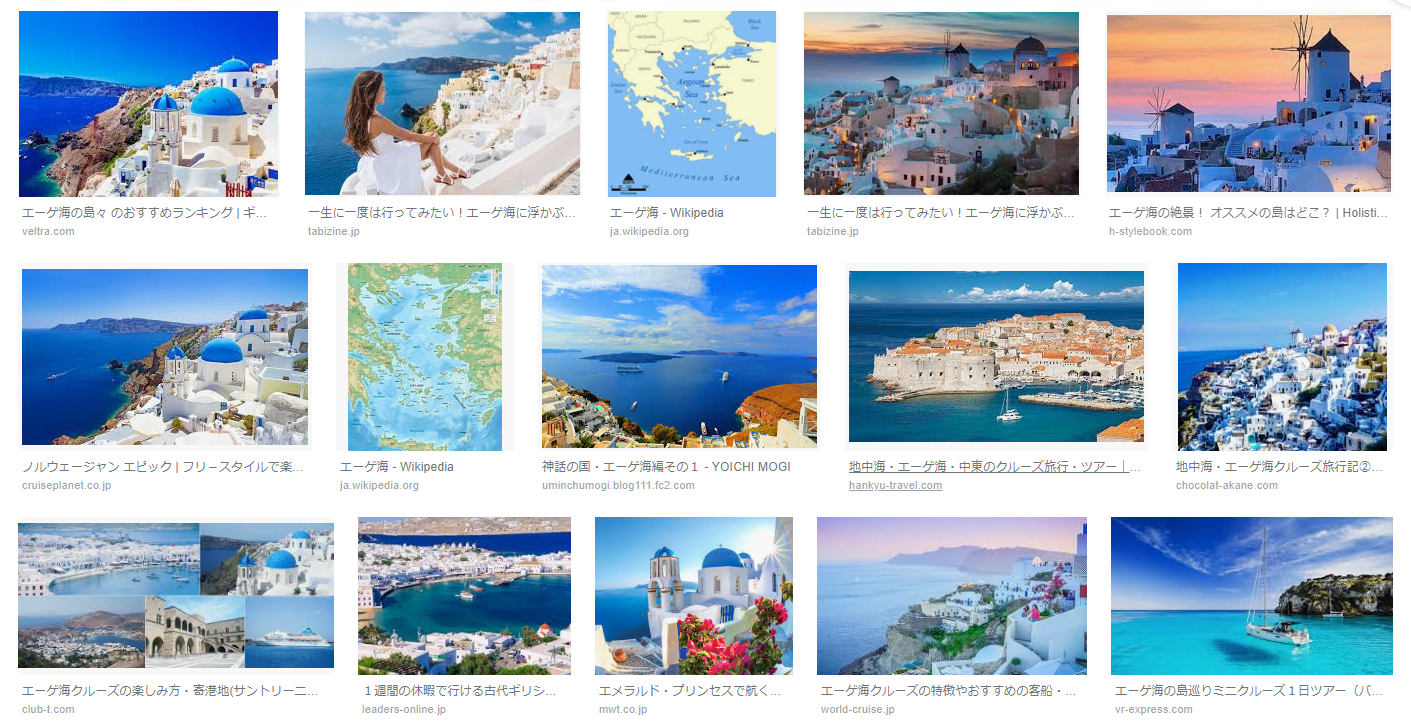
コメント