橋下徹の印象
橋下氏が府知事(2008年就任)、大阪市長(2011年就任)時代に、やるべき事をやり尽くした感じがします。あの頃は県外から見ていても惚れ惚れするような活躍ぶりでした。
その後は「弁が立つ橋下氏が理屈で人をやり込めて嫌味な人」に見えてきてしまいました。
本人も議論が多方面で炎上したことは否定していない
強引な手法や、公務員や反対派を鋭く糾弾する姿勢、メディアでの理屈を武器にした激しい討論姿勢が「嫌味で攻撃的」と受け取られ、支持者以外からは批判も集まりました。本人も議論が多方面で炎上したことは否定していません。
改革の“やり尽くし感”と同時に、政治的なカリスマ性ゆえに賛否が分かれやすくなり、2023年ごろには支持基盤を引き継いだ吉村洋文知事らが継続して改革を推進しています。橋下氏はその後、政界を離れ、弁護士やメディア活動に軸足を移しています。総じて、改革の実績は鮮烈で大阪の構造を変える大きな功績を残した一方で、政治家としての振る舞いが好悪を分けた存在と評価されています
橋下氏の強硬かつ対立的なスタイルは国会議員向きではない
幅広い合意形成が求められる国政の場では、橋下氏の強硬かつ対立的なスタイルは必ずしも適合しにくい面があります。実際、2015年に大阪都構想の住民投票で僅差ながら否決され、その後は政界を引退し、政治家としての活動から一線を退いています。この引退の背景には、政治的敗北だけでなく、激しい賛否両論の中での政治的疲労感や限界もあったと推察されます。
一方で、橋下氏の改革的手腕とカリスマ性は大阪の政治に革新をもたらし続け、大阪の政治基盤を大きく変えたことは確かです。国会議員としての適性を問えば、現在の国政の調整や対話重視の環境には合わない部分もありますが、地方政治や政策推進においては革新の原動力となりました。従って、「賛否が分かれる橋下氏は国会議員には不向き」との評価には一定の妥当性がありますが、彼の政治姿勢と実績を正しく理解することが重要です
大阪を持続可能な都市運営へ変え、政治風土を刷新した
橋下徹氏が大阪府知事(2008年就任)、大阪市長(2011年就任)を務めたことで、大阪は大きく変わりました。具体的な変革は以下のとおりです。
行政改革・財政健全化の推進が最大の特徴です。橋下氏は6兆円近い借金を抱えていた大阪府の財政再建を最重要課題に据え、職員数・給与カットを含む大幅な支出削減を断行しました。従来の労使癒着や無駄な行政を排し、外郭団体の整理統合も敢行しました。これにより府の財政悪化を抑え、行政運営のスリム化・効率化を実現しました。
また、大阪、市の二重行政の打破や市営地下鉄・バスの民営化、関西空港・伊丹空港の統合・民営化、府立と市立大学の統合など、大規模な行政機構の統合と再編を進め、財政負担の軽減とサービスの合理化を図りました。
選挙で改革派が多数派となり政治基盤を固めたことで、改革に必要な政治的推進力を確保。これらが大阪の持続可能な都市運営への道を開き、政治風土を刷新しました。
こうした大胆な行政改革が、橋下改革以後の大阪の大きな変貌の実態です。改革の推進者として吉村洋文知事が継承し、今後も大阪発の改革モデルが国政に波及する期待が高まっています。
大阪における「維新の会の実績と、従来の状況からの変化」
大阪維新の会は2010年に大阪府の自民党改革派議員が離脱して結成され、橋下徹元知事、松井一郎元市長らのリーダーシップのもと急速に勢力を伸ばしました。設立後1年で大阪府議会、市議会で過半数を獲得し、旧来の自民党主導の旧態依然とした政治体制から刷新しました。大阪は中央からの過剰な規制や財源流出による衰退を経験していましたが、維新は保守的思想を持ちつつも実務面では革新的な改革を推進しています。自民党の変化が見られないならば改革派が政権を奪取するという実務的合理的な発想で、大阪の自民党は事実上解体・刷新されました。
維新の会は行政機能の統合や財政再建、公共インフラ投資、効率的な地方自治の実現に努め、大阪府と大阪市の首長が密接に連携している点も特徴です。維新は「大阪都」構想を中心に据え、大阪市の権限と財源を府へ集約する政治体制改革を掲げましたが、住民投票で2度否決されるなど反発もありました。また、新型コロナ対応の致死率や財政力指数に課題が指摘される一方、一定の改革実績と支持を獲得しています。
従来の自民党政治が既得権益と中央依存で大阪の衰退を招いたのに対し、維新は実務的かつ地方分権に基づく行政改革を進め、政治の効率化と財政健全化を追求したことが大きな変化です。国政の自民党とは異なり、維新は大阪独自の地域政党として改革実績を積み上げ、2010年代以降の大阪政治の主役になりました。
このように大阪維新の会は、旧来の旧態依然とした地方自民党政治を刷新し、政治の実務的改革と地方自治の効率化を実現しようとした点で、大阪の政治状況を大きく変えました。国政においても維新は大阪の基盤を固めており、大阪を中心にした改革潮流を牽引しています。
大阪維新の会は元自民党系議員が多い
大阪維新の会は結成当初、自民党大阪府連所属の地方議員の中で橋下徹知事支持派が自民党を離脱して結成されました。設立時は自民党系議員が多く参加しており、その後も自民党や民主党の議員が次々と加入して勢力を拡大しました。特に2010年当時の自民党大阪府連議員の多くが維新に移った経緯があります。これにより、大阪維新の会は元自民党系議員が多い地方政党とされています。
2025年10月18日 自維連立協議で大阪自民に動揺…「副首都構想は絶対のめない」「維新政権入りなら自民府連は消滅の可能性も」
この記事は、自民党と日本維新の会による「連立政権樹立に向けた政策協議」に関して、大阪自民党内で不安と反発が広がっている様子を伝えている。以下に主な内容を整理する。
概要
- 高市早苗総裁の下で、自民党と維新の連立協議が進行中。
- 大阪では長年、自民と維新は対立関係にあり、協議開始が府連に動揺を与えている。
- 公明党の連立離脱(10月10日発表)が契機となり、維新への接近が加速した。
大阪自民の反応
- 松川るい大阪府連会長代行は「大阪の特殊事情がある」として、府連の独自路線維持を主張。
- 昨年の衆院選で、大阪の小選挙区19区中15区に立候補した自民候補が全敗するなど壊滅状態。
- 一部府連幹部は「維新連立入りなら自民府連は消滅しかねない」と危機感を示す。
- 維新の掲げる「副首都構想(実質的に大阪都構想を前提)」を巡り、「絶対に受け入れられない」という強硬意見も出ている。
公明党の立場
- 公明は大阪で長年、自民と選挙協力関係を築いてきたが、前回衆院選で維新に全敗。
- 連立離脱後も、大阪では自民と協力方針を維持する意向だった。
- しかし、自民・維新の接近で「今後の支援関係が困難になる」との不安が強まっている。
- 公明内部では「有権者が『自公より自維の方がいい』と思うようになれば厳しい」という声も出ている。
背景と影響
- 高市政権において、維新を与党に取り込むことで国政安定を狙う一方、地方、特に大阪では党組織再編のリスクが浮上。
- 大阪自民・公明双方にとって、「維新との関係をどう扱うか」が今後の生き残りを左右する焦点となっている。
2025年10月21日 「維新とはバチバチ、みんなポカン」自民大阪に渦巻く不満 「まずは首相指名」と賛同も
この記事は、2025年10月21日付の産経新聞によるもので、自民党と日本維新の会による連立政権成立を受けた「自民党大阪府連」の動揺と対立感情を報じている。
自民党と維新はこれまで大阪で激しく競い合ってきた経緯があり、両者の連立は「不倶戴天の敵」とまで言われた関係を覆すものとなった。府連の中では、賛否両論が渦巻いている。
- 府議団政調会長の中井源樹氏は、「高市早苗総裁を首相にするのが最優先」として、党本部の決断を支持。思想的な共通点や「大阪を良くしたい」という目的の一致を理由に挙げた。
- 元衆院議員の中山泰秀氏も、維新との大同団結を評価し、「大阪自民は終わらない」と強調した。
- 一方で、別の自民元衆院議員は「首相指名のための数合わせでは駄目だ」と批判。選挙区調整によって維新優位が固定化され、自民が大阪で埋没する危険性を指摘した。
さらに、府連関係者の間では「維新とは激しく戦ってきたのに唐突だ」「府連消滅の恐れもある」との危機感が強い。維新がかねて掲げる「副首都構想」に対しても、自民側の反発は根強く、両党の協力体制が今後どこまで機能するかは不透明だ。
要するに、高市政権誕生を目的とした自民・維新連立だが、大阪では「共闘による国政的打算」と「地元組織の存立危機」が衝突しており、火種は依然として燻っている。
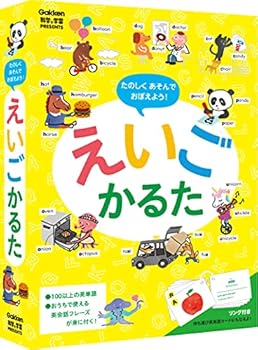
コメント