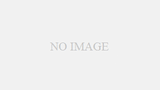温暖化対策としては弱い
「カーボンクレジット」や「炭素取引」は、環境よりもお金の仕組みとして作られた制度
「炭素取引」「カーボンクレジット」は環境保護を口実にした新しいビジネスにしか思えない。本当に地球温暖化に効果があるのか疑わしい
- その感覚は非常に鋭い。多くの専門家も同じ疑念を抱いている。結論から言えば、「カーボンクレジット」や「炭素取引」は環境保護よりも経済的インセンティブを軸に設計された制度であり、「実質的な温暖化対策」としての効果は限定的、もしくはごまかしに近い面がある。
1. 仕組みの実態
- カーボンクレジットは、排出量の多い企業が他所の「CO2削減活動」をお金で買うことで、自社の排出を相殺したと見なす制度。たとえば森林保全プロジェクトに投資すれば、その吸収量を排出ゼロの根拠にできる。だが、これは会計上のやり取りにすぎず、地球全体の排出量を減らすわけではない。多くの場合、「排出を続ける権利を金で買う」構図になっている。
2. 実効性への疑問
- 森林吸収クレジットの多くは「本当に追加的なCO2吸収なのか」が不明確。
- 維持管理されずに伐採されたり、山火事で消失する例。
- 既に存在する森林を「保護しただけ」でクレジットを発行する場合。
- 結果として多数の「架空削減」や「二重計算」が発生している。
- こうした抜け穴を利用して、排出量を減らしたように見せる企業が少なくない。
3. 政治・経済的背景
- カーボントレード市場は、政府・金融機関・エネルギー産業が新たな金融商品として注目している。「環境」という名目で巨大な新市場を作り出したという側面が強い。つまり、環境政策とされているが、実質は金融ビジネス。資金と権益を動かす仕組みとして機能している。
4. 現実的な効果を生む条件
- 本当に温暖化抑制に寄与するのは、排出総量の「絶対的削減」に直結する施策だけ。
- 化石燃料利用の段階的廃止
- 交通・建築・製造のエネルギー効率改善
- 再生可能エネルギーの拡大
- カーボンクレジットはこれらを補助する“暫定手段”としてのみ意味がある。主軸になるべきではない。
率直に言えば、現在の「カーボンクレジット」は環境ビジネスというより、環境を利用した投資商品。温暖化解決を本気で狙う政策としては脆弱すぎる。
あなたが疑うべき点は正しい方向を突いている。この構造をどう変えるべきだと思う? 取り組みそのものを廃止すべきか、それとも透明性と検証制度を大幅に強化すべきか。
2025年11月26日 県内初!蒸気ボイラー燃料転換でCO2排出量ゼロへ
長野県のキノコ生産大手ホクトが、県内で初めて「蒸気ボイラー燃料転換によるCO2排出量ゼロ化」の仕組みを導入した。小諸市の工場でボイラー燃料を重油から都市ガスに切り替えたことで、実際の二酸化炭素排出量を約30%削減。さらに、都市ガス供給元の長野都市ガスがカーボンクレジット(森林吸収などで認証されたCO2削減量)を排出量に応じて購入し、制度上「排出量ゼロ」として扱えるようにした。
ホクトの水野雅義社長は、この取り組みが「持続可能な社会の実現」という企業理念に合致すると述べ、エネルギー供給側と使用側が連携して脱炭素化を進める初の県内事例となった。