2025年10月06日 プーチンが頭を抱える姿が目に浮かぶ…「ソ連崩壊直後に逆戻り」小麦と中国車を”物々交換”するロシアの窮状
ロシアはウクライナ侵攻に伴う西側諸国の経済制裁で国際送金網から締め出され、1990年代以来となる物々交換取引が復活している。中国車を小麦で支払うなど、金属・農産物と完成品を交換し、中国銀行が二次制裁を回避する仕組みが広がっている。パキスタンともひよこ豆とコメ、ミカンなどの交換を行い、政府は企業向けガイドまで作成し推奨している。
経済は制裁と戦費増大で冷え込み、GDPは縮小、財政赤字は年間目標超過、ガソリン価格は30%以上上昇し市民生活を圧迫。木材や油菜種など原材料輸出で中国への依存が強まり、かつて技術援助をしていた立場は逆転し「中国の経済衛星」化が進行。中ロ貿易は過去最高だが、ロシアは原材料供給国化し、製造業シェアは世界の1.33%にとどまる。
物々交換は制裁逃れとしては有効だが根本解決にはならず、国際金融システムから孤立したロシアの脆弱さを象徴。プーチン政権は戦争継続を優先し国力低下と民間経済の疲弊を招き、長期化すれば状況は一層深刻化すると見られている。
「伝統的価値観」を前面に押し出し、西側の「進歩的」文化に対抗
2025年10月01日 ロシア政府がポップカルチャーを利用、戦況から大衆の注意をそらすためか
この記事は、ロシア政府がウクライナ侵攻の長期化と経済悪化から国民の注意をそらすため、ポップカルチャーを利用している実態を指摘している内容です。
戦争と経済的行き詰まり
- ロシアは3年半以上続く侵攻で1日あたり約10億ドルという膨大な費用を費やしている。
- 経済は一時的な好景気を過ぎ、前例のない行き詰まりに直面している。
- 政府は公式には「順調」と発表しているが、実態は深刻化している。
注意そらしのためのポップカルチャー利用
- モスクワではライトショー、フェスティバル、テーマパークなどの祝祭イベントが頻発。
- EDMやK-POPを含む大規模フェス「ポルタル2030-2050」が開催され、10万人超を動員。
- イベントは「モスクワを流行の発信地」と印象付け、若者世代を「政治よりポップカルチャー」に引き込む狙いがある。
- 一部西側の著名人も参加し、国際的な印象操作も進めている。
政府のソフトパワー戦略
- 従来の宣伝に加え、サブカルチャー外交を展開。
- 「ユーロビジョン」に対抗する国際歌謡コンテストを創設し、ソ連時代の歌謡イベントを復活。
- 「伝統的価値観」を前面に押し出し、西側の「進歩的」文化に対抗している。
本質的な問題点
- こうした文化的演出は一時的効果しかなく、持続可能ではない。
- 歴史が示すように、軍事優先の経済はやがて「バターもパンも失う」と記事は指摘する。
米国の動向
- これまでロシア寄りだったトランプ大統領が9月に入って突如方針転換。
- Truth Socialに「ウクライナは全土を奪還できる」と投稿。
- ロシア経済の疲弊と戦争継続の限界を見通した兆候とみられる。
記事全体を通じて、ロシア政府が「ポップカルチャー外交」によって国内外の注意を逸らそうとしている姿を描きつつ、それが長続きせず、いずれ国民が現実に直面せざるを得ないという警鐘が示されています。
「軍事優先の経済はやがてバターもパンも失う」とは
軍事費や軍備増強に経済資源を偏重させると、一般の生活必需品である食料や日用品などが不足したり、生活が苦しくなったりするという意味の言葉です。つまり、戦争や軍事拡大に経済の多くを注ぐと、国民の生活に必要な基本的なものが手に入らなくなり、経済的にも社会的にも大きな損失を被るという警告的な表現です。
この言葉は、軍事優先政策が経済のバランスを崩し、国民生活への悪影響が最終的に深刻化することを指摘しています。戦争準備や軍事費の過剰投入は、食料生産や流通、一般消費財の確保がおろそかになるため、生活の基盤である「バター(パンとともに象徴的な食糧)」すら失う事態に陥るという歴史的な教訓や批判の一つです。
ウディ・アレンやリュック・ベッソンが参加
モスクワでの大規模な電子音楽フェスティバル「ポルタル2030-2050」などのポップカルチャーイベントに参加した一部の西側有名人として、映画監督のウディ・アレンやリュック・ベッソンが挙げられています。彼らはブラックリスト入りの危険性がある中でも実際に現地に足を運んでいるか、一部はオンライン参加をしているとのことです。
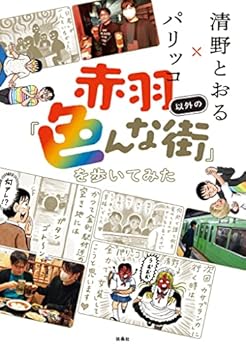
コメント