DIME(ダイム)とは
- 外交(Diplomacy)
- 情報(Intelligence)
- 軍事(Military)
- 経済(Economy)
2025年10月01日 「太った将軍は容認できない」と言い放ったヘグセス氏 危ぶまれる日米「ワンチーム」の崩壊
この記事は、ヘグセス米国防長官が9月30日に行った米軍将官らへの演説を巡る分析です。ヘグセス氏は「太った将軍は容認できない」と述べ、軍内の規律や身だしなみの重要性を強調するとともに、多様性・公平性・包摂性(DEI)への過度の傾斜を批判しました。背景には「軍は戦闘に専念すべき」というトランプ政権中枢の発想がありますが、米軍の現場では情報戦や認知戦を含む総合的な安全保障戦略(DIME)を重視する傾向があり、双方の間に亀裂が生じています。
ヘグセス氏の主張
- DEIの推進を「行き過ぎ」と批判
- 「太った将軍は嫌気がさす」と発言し、軍人の外見や規律を重視
- 軍は戦闘に専念すべきで「頭でっかちの軍人」は不要との含意
背景と対立の構図
- 米軍内ではアフガンやイラク戦争で勝利しながら戦略的に失敗した経験から、DIMEを重視し情報戦・認知戦への対応を強めてきた。
- トランプ政権やヘグセス氏はそれを否定し、「戦闘=軍の本分」という姿勢を強調。軍内分裂の火種となり得る。
国防総省と現場の乖離
- 国防総省は間もなく新しい国家防衛戦略(NDS)を発表予定だが、政権中枢は「国外紛争には関与しない」方針を基本にしている。
- 現場の米軍は同盟国との信頼関係構築を重視してきただけに、対立が先鋭化する可能性がある。
日米同盟への影響
- 米軍は従来から日米共同訓練で「ワンチーム」を強調しており、同盟国重視の姿勢を持っていた。
- 外務省幹部からも「日米同盟一本やりで大丈夫か」という不安が台頭。
- 米軍人たちは今後、シビリアン・コントロールへの遵守と自身の職業意識との間で板挟みになり、葛藤が増える懸念がある。
この記事は「軍の在り方を戦闘一点に絞りたい政権中枢」と「総合戦略を重視する現場」の間に広がる断絶を描き、日米「ワンチーム」体制の揺らぎを指摘しています。
日米同盟への影響
まず、ヘグセス氏は多様性推進の過度な進展や軍人の肥満などの問題を軍の規律の観点から批判し、戦闘に専念するべきという考えを重視しています。一方で、米軍内部や日本側の防衛関係者は、情報戦や認知戦を含む総合的な安全保障(DIME)戦略の重要性を認識しており、その方向性に対立があります。
2025年3月の日米防衛相会談では、ヘグセス国防長官と日本の中谷防衛大臣が「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて協力し、日米同盟の抑止力・対処力の強化を確認しています。また、日本の南西諸島における日米共同プレゼンスの強化や即応性向上のための訓練・演習も議論されています。米国は核を含むあらゆる能力で日本防衛に揺るぎなくコミットする姿勢を示しています。
しかし、ヘグセス長官の指示で進められている新たな国家防衛戦略(NDS)では、米国は米本土防衛と対中抑止を優先し、陸上戦力の合理化と海空戦力・ミサイル・ドローンの強化を目指しているため、陸軍に依拠した伝統的な戦闘要素とのバランスに課題があります。
またトランプ政権の中枢はウクライナ戦争への介入回避を基本方針とし、これが現場の米軍の同盟国重視の姿勢と乖離を生み、日米「ワンチーム」体制の亀裂を懸念させています。
要点としては、
- 日米同盟自体は引き続き強化を確認し、特にインド太平洋の安全保障で緊密連携が図られている。
- しかし、米軍トップのヘグセス氏の姿勢は軍の規律や戦闘専念を強調し、軍内外の情報戦重視路線と衝突している。
- 政策の食い違いが日米同盟の運用面で摩擦や亀裂を生む懸念がある。
- 今後、米軍内の分裂や政治と軍の関係をめぐる葛藤が深まる可能性がある。
従って日米同盟の対外的な枠組みは維持強化されながらも、内部的な意見対立は対日含めた連携に影響を及ぼしかねない複雑な局面にあります。
2025年10月01日 ヘグセス米国防長官 米軍戦闘力強化策を発表 体力テスト義務化 左派が唱える社会正義排除へ
2025年9月30日、アメリカのヘグセス国防長官はバージニア州での軍事高官会議で、米軍戦闘力強化のための新方針を発表した。全兵士に男女共通の厳格な体力テストを課し、基準未達成者は退役させると明言し、同時に左派的な「社会正義」や政治的配慮を徹底的に排除する姿勢を強調した。
- 体力基準の義務化
全兵士は年2回の体力測定と身長・体重測定をクリアする必要があり、戦闘要員は男性基準の70%以上を求められる。達成できなければ退役処分となる。 - 男女共通の基準
女性兵士も高水準の体力基準を満たすことが必須。貢献を認めつつも「戦場では性差は通用しない」と明言した。 - 社会正義の排除
DEI(多様性・平等・包摂)オフィスやアイデンティティ月間は廃止。気候変動を前面に出す姿勢も撤回。収入格差、LGBTQ、人種・性別問題など「政治的要素」に起因する制度は不要とする方針。 - 「戦士精神」の再構築
米軍は「防御的存在」ではなく「勝利のための戦士」を育成すると強調。交戦規則や過剰な配慮の排除を掲げ、徹底した実戦力追求を目指す。 - 肥満や体力不足の容認否定
階級を問わず肥満は不適格とされ、全員が国防長官自身と同じく厳格な体力訓練を行うべきだと主張。
背景と意味
- この方針は、米軍内部における「社会的イデオロギーの影響排除」と「戦闘即応力向上」を狙ったもの。特に近年議論を呼んでいた性別基準の違いや多様性プログラムを撤廃し、純粋に軍事力・戦闘力強化に集中する姿勢が鮮明になった。
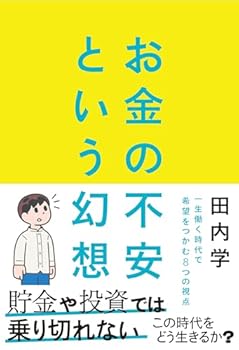
コメント