- 欧米の圧力だけで体制を転換させるのは難しい
- 2025年10月18日 ミャンマーで臓器を売る人が急増中 軍事政権下で経済混迷、「生きるために」 ミャンマーで経済の崩壊や内戦の長期化によって、臓器売買に走る人々が増加している実態を伝えている。主な内容をまとめると次の通り。 ミャンマーでは2021年の軍事クーデター以降、失業と物価高が深刻化。生活苦から借金返済のために腎臓などの臓器を売る人が激増している。ヤンゴン近郊のカンベ村では、住民の多くが臓器販売を経験し、腎臓1つあたりの相場は約700万チャット(約25万円)。 臓器は主にインドの病院で移植され、ブローカーが偽造書類を用意して「親族からの提供」と装う仕組みが確立している。摘出手術を受けた後、仲介役として他人を紹介して報酬を得る人も出ている。 多くの人は「生きるため」「借金返済のため」と語るが、得た金もすぐに生活費で消え、結局何も残らないという声が多い。また、手術を受けたことを証明する書類があると徴兵を免れるとの理由で、軍政下で黙認されているケースまである。 姉妹や若い母親たちの証言からは、民主派指導者アウンサンスーチー氏への郷愁と軍政への深い絶望が読み取れる。臓器を売っても生活は改善せず、「生きるために体を削る」極限の現実が浮かび上がっている。 2013年06月17日 ミャンマーのかつての友人、中国はどこで間違えたのかと思い悩んでいる
- 2013年01月15日 アジア諸国で高まる反中国感情
欧米の圧力だけで体制を転換させるのは難しい
- ミャンマーは地政学的にインド洋と中国南部を結ぶ要衝に位置し、そのため欧米と中国の双方が深く関わってきた。歴史的経緯と現在の状況を整理すると次のようになる。
中国との関係
- 中国は長年、ミャンマー軍政の最大の支援国として経済・軍事両面で関与してきた。欧米が人権問題などを理由に制裁を科した際、中国は石油・天然ガス、鉱物資源への投資やインフラ建設を進め、事実上の後ろ盾となった。
- 2017年のロヒンギャ危機でも中国は国連非難決議に反対し、ミャンマーを擁護した。2020年には習近平国家主席が訪緬し、「中国・ミャンマー経済回廊(CMEC)」構想の下、鉄道・高速道路、深海港と経済特区など33の協定を締結して関係をさらに深化させた。
欧米との関係
- 欧米諸国(米国・EU)は1988年以降、民主化運動弾圧を受けてミャンマー軍政を「圧制」として制裁を科した。
- 民政移管後は関係改善が進み、欧米の投資が一時再開されたが、2021年の軍事クーデター以降、再び制裁路線へ逆戻りした。米国・英国・EU・カナダは軍関係者と国営企業への資産凍結や取引禁止を実施し、2024年末時点でも制裁を強化している。
- ただし、ロシアや中国が軍事支援を続けるため、欧米の圧力だけで体制を転換させるのは難しい状況が続いている。
現在の構図
- 現在のミャンマー情勢では、欧米の制裁と中国・ロシアの支援という「二極構造」が鮮明になっている。国軍は欧米からの経済的孤立を、中国の投資やエネルギー協力で補おうとしており、特に雲南省経由の輸送路線や港湾開発がその生命線になっている。
- 一方、欧米は人権と民主主義を重視する立場から制裁を続けており、国際外交上、ミャンマーは「米中対立の縮図」の一角を占める存在となっている。
2025年10月18日 ミャンマーで臓器を売る人が急増中 軍事政権下で経済混迷、「生きるために」 ミャンマーで経済の崩壊や内戦の長期化によって、臓器売買に走る人々が増加している実態を伝えている。主な内容をまとめると次の通り。 ミャンマーでは2021年の軍事クーデター以降、失業と物価高が深刻化。生活苦から借金返済のために腎臓などの臓器を売る人が激増している。ヤンゴン近郊のカンベ村では、住民の多くが臓器販売を経験し、腎臓1つあたりの相場は約700万チャット(約25万円)。 臓器は主にインドの病院で移植され、ブローカーが偽造書類を用意して「親族からの提供」と装う仕組みが確立している。摘出手術を受けた後、仲介役として他人を紹介して報酬を得る人も出ている。 多くの人は「生きるため」「借金返済のため」と語るが、得た金もすぐに生活費で消え、結局何も残らないという声が多い。また、手術を受けたことを証明する書類があると徴兵を免れるとの理由で、軍政下で黙認されているケースまである。 姉妹や若い母親たちの証言からは、民主派指導者アウンサンスーチー氏への郷愁と軍政への深い絶望が読み取れる。臓器を売っても生活は改善せず、「生きるために体を削る」極限の現実が浮かび上がっている。 2013年06月17日 ミャンマーのかつての友人、中国はどこで間違えたのかと思い悩んでいる
- 以前のミャンマーは中国の「衛星国家」とも言えるほど北京に依存していましたが、民主化と経済開放の流れの中で中国離れが進んでいます。
- ネピドーで開催された世界経済フォーラムでは、世界900人以上の参加者の中で中国企業関係者はわずか16名と存在感が薄く、中国の影響力低下を象徴する場面となりました。
- その原因として、中国側の「傲慢」「怠慢」「人民解放軍による過度な干渉」が挙げられ、関係悪化の要因となったと指摘されています。
- ミャンマー側は軍政時代から中国依存を減らす必要を感じ、アメリカ・日本・ASEAN・欧州などとの関係強化を進め、多極外交を志向しています。
- アウンサンスーチー氏は「賢明な国際関係の舵取り」が必要だと語り、中国との関係維持も一方で重視する姿勢を示しました。
- 中国政府内では「誰がビルマ(ミャンマー)を失ったのか」という問いが広がっており、過去の「誰が中国を失ったのか」というアメリカ外交史上の問いを想起させます。
- 最終的に、中国が最も恐れているのは、ミャンマーにおける「民主化の波」が中国国内に波及することだと結論づけています。
2013年01月15日 アジア諸国で高まる反中国感情
アジア各国で進む中国資本主導の経済進出がもたらす住民感情の悪化を報じています。
ミャンマーの歌手リンリンが人気を得た理由の背景には、中国人移民によって地域社会が変わっていくことへの不満や不安があります。特に、彼が故郷マンダレーの変貌を歌う曲が人々の共感を呼び、それを象徴的に描いていると記事は紹介しています。
また記事全体では、
- 中国の経済的拡大による地元産業・資源支配への反発
- 中国系移民の増加による文化・雇用摩擦
- ミャンマー、ベトナム、フィリピンなどでの実例紹介
といった要素を挙げ、アジア全体で高まりつつある「反中国感情(anti-China sentiment)」の潮流を分析しています。
自転車旅の紀行文です。世界一周を成し遂げた著者が日本各地を自転車で巡り、その旅で出会った風景や人々、食文化を生き生きと描いています。宮崎の地鶏や北海道のウニ、そば街道やうどんの聖地など各地の名物を堪能しながら、色街の面影が残る島にも上陸。旅先での語らいや飲み会、歌や踊り、時に涙する感動的な体験も綴られています。世界を見た後に改めて日本の魅力を再発見する内容で、旅の楽しさと深さが伝わる作品です。自転車旅ならではの自由さや、人との出会いを楽しむ心持ちが読者に旅心を呼び起こします。
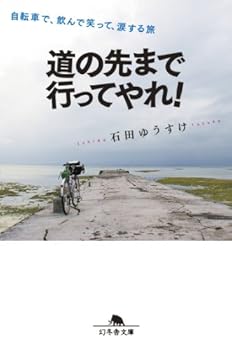
コメント