お蔭参り(おかげまいり)
Wikipedia
江戸時代に起こった伊勢神宮への集団参詣。お蔭詣で(おかげもうで)とも。数百万人規模のものが、およそ60年周期(「おかげ年」と言う)に3回起こった。お伊勢参りで抜け参りともいう。
お蔭参りの最大の特徴として、奉公人などが主人に無断で、または子供が親に無断で参詣したことにある。これが、お蔭参りが抜け参りとも呼ばれるゆえんである。大金を持たなくても信心の旅ということで沿道の施しを受けることができた時期でもあった。
江戸からは片道15日間、大坂からでも5日間、名古屋からでも3日間、東北地方からも、九州からも参宮者は歩いて参拝した。陸奥国釜石(岩手県)からは100日かかったと言われる。
Perplexyty
お蔭参り(おかげまいり)とは、江戸時代に起こった伊勢神宮への大規模な集団参詣のことを指します。特に1650年(慶安3年)、1705年(宝永2年)、1771年(明和8年)、1830年(文政13年・天保元年)に約60年周期で大規模な「おかげ年」と呼ばれる群参が起こり、数百万人が伊勢に参拝しました。
特徴的なのは、奉公人や子どもたちが主人や親に断りなく家を抜け出して参拝に向かったため、「抜け参り(ぬけまいり)」とも呼ばれました。この行動は当時は善行とみなされ、沿道の住民や富豪から食事や宿泊の施し(せぎょう)が施されるなど、信仰心をもとにした人々の支え合いの旅でもありました。
「お蔭参り」の名称の由来には諸説あり、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の「おかげ」(御利益や加護)によって参詣が叶ったことや、旅の途中で多くの人々の「おかげ」で助けられたこと、平和な生活への感謝を意味するとされています。
また、群参の際には「おかげ踊り」と呼ばれる踊りが広まるなど、社会的な現象としても大きな影響を持ちました。これらの参詣は民衆のエネルギー表現としても評価されており、一部は後の「ええじゃないか」という社会運動にもつながりました。
まとめると、お蔭参りは江戸時代に定期的に起こった大規模な伊勢神宮への民衆の集団参拝で、信仰と社会的連帯が特徴の歴史的行事です。
ええじゃないか
Wikipedia
日本の江戸時代末期の慶応3年(1867年)8月から12月にかけて、近畿、四国、東海地方などで発生した騒動。「天から御札(神符)が降ってくる、これは慶事の前触れだ。」という話が広まるとともに、民衆が仮装するなどして囃子言葉の「ええじゃないか」等を連呼しながら集団で町々を巡って熱狂的に踊った。
伊勢神宮に御札が降るおかげ参りと違い、ええじゃないかの御札は地域で信仰されている社寺の御札が降ったため、現地で祭祀が行われる事が多かった[1]。降札があると、藩に届け出た上で屏風を置く、笹竹で家を飾る、酒や肴を供えるなどして町全体で札を祀った。名古屋の場合、降札後の祭事は7日間に及び、その間は日常生活が麻痺した。
Perplexyty
「ええじゃないか」は、19世紀日本の一種の民衆運動・風俗現象を指します。特に1867年(慶応3年)頃に、東日本を中心に広まった大衆の集団的な踊りや騒動のことです。
この「ええじゃないか」は、当時の社会不安や政治的混乱、赤報隊や新政府の登場などの動揺の中で、民衆が神がかり的な熱狂状態に陥り、集団で踊りや祝祭行動を繰り返したものでした。参加者たちは「ええじゃないか」と叫びながら踊ったため、この名前がつきました。
起源は不明ですが、天変地異や社会的変革への不安、飢饉や経済的困窮などが背景にあったとされ、一種の民衆のカタルシスや抵抗表現、または宗教的・精神的な癒しの側面も指摘されています。
簡単にまとめると、「ええじゃないか」とは1860年代の日本で起きた民衆の踊り騒ぎの怨念や解放感を表した社会現象の名前です。
赤福餅のCMでも表現されている
写真家Kankanによる伊勢神宮の最新ガイドブックです。初めての参拝者はもちろん、何度も伊勢神宮を訪れている方にも新たな発見がある内容となっています。令和版では、内宮・外宮の参拝ガイド、御神楽や参拝マナーといった基礎情報に加え、近年の参拝の新常識についても解説されています。伊勢神宮の年間約1,500もの祭事、神宮の美しい自然など、現在の伊勢神宮が圧巻の写真とともに紹介されており、眺めるだけで神宮の雰囲気を感じられる永久保存版となっています。
情報は、2018年に刊行された同書の改訂・加筆版ですが、地元クリエイターによる穴場情報や、地元女性に人気のおしゃれな雑貨、カフェ、食事処、宿泊情報も豊富に掲載されています。特に、参宮の際に訪れたいおすすめスポットや、一度は泊まってみたい憧れの宿、神宮参拝に集中できる立地の宿も紹介。参拝の作法やマナー、御神楽について丁寧にまとめられているので、初心者でも安心して参拝できます。
伊勢神宮の「今」を知りたい方には、写真を含めて臨場感のある一冊です。




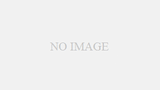
コメント