メタンハイドレートの例があるから期待しすぎないように
スイートソルガムは年に2回収穫可能
スイートソルガムは年に2回収穫可能なことが特徴で、特に暖地や温暖地ではその再生力を活かして多回刈り(2回以上の収穫)が行われます。ただし、気候や品種によっては1回の収穫のほうが収量が多くなる場合もあります。日本の一部地域では1回刈りが推奨されることもありますが、条件が整えば2回収穫が可能です。
一方、サトウキビは生育期間が12~18ヶ月と長いため、通常は年1回収穫が基本です。亜熱帯〜熱帯地域での栽培で、多収穫のために栽培管理を工夫するケースもありますが、2回収穫は一般的ではありません。
トウモロコシは一般的に生育期間が約3~4ヶ月で、年に1〜2回の収穫が可能な場合がありますが、バイオエタノール向けの大規模生産では多くは年1回収穫です。栽培地の気候や栽培方法によっては年2回収穫も可能ですが、慣行的な生産方法では1回が主流です。
| 作 物 名 | 年間収穫回数 | 備 考 | 1haあたりの エタノール収量 |
|---|---|---|---|
| スイートソルガム | 1~2回 | 暖地では2回刈り可能、再生力が強い | 約3.4〜4.4トン |
| サトウキビ | 通常1回 | 生育期間長く多収穫は難し | 約3.1〜5.5トン |
| トウモロコシ | 1~2回(主に1回) | 地域と栽培条件によるが年1回が一般的 | 約1.9トン |
2025年10月19日 成田空港が描く「航空燃料の地産地消」の全貌
このフォーブスジャパンの記事「成田空港が描く『航空燃料の地産地消』の全貌」は、成田国際空港株式会社(NAA)が主導する脱炭素化の実証プロジェクトを紹介している内容である。
このプロジェクトでは、空港周辺の騒音対策用地約1000平方メートルで、名古屋大学が開発したスイートソルガム新品種「炎龍」を栽培し、その茎に含まれる糖分からバイオエタノールを生成する。このエタノールを、神戸大学が開発した技術を用いて精製し、最終的には地元企業が持つATJ(Alcohol to Jet)技術によって航空燃料SAFへ転換する仕組みとなる。
炎龍は、痩せ地でも生育でき、1年に2回収穫可能で、通常種の2倍以上の糖蜜を生成する高収量品種である。搾りかすは家畜飼料としても活用できるため、食料との競合がない。また、成田空港は「サステナブルNRT2050」構想のもと、2050年までに空港運営由来のCO₂排出ゼロを目指しており、今回の「地産地消型SAFモデル」がその中核施策に位置づけられる。
プロジェクトでは、名古屋大学、神戸大学、地元農業法人HSS、ちばぎん総合研究所が連携して試験的に運用し、将来的に地域産業全体での脱炭素化を目指す構想である。この取り組みが実用化されれば、航空燃料の輸送依存を減らしながら、農業振興・CO₂削減・地域経済の活性化を一体的に実現する地域完結型モデルとなる。
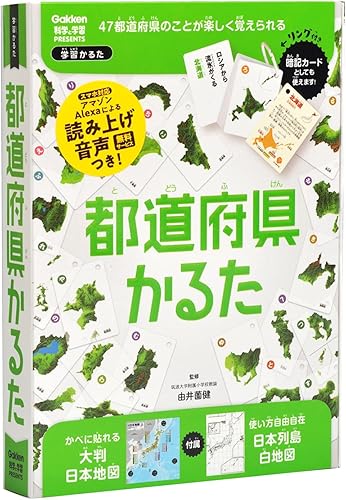
コメント