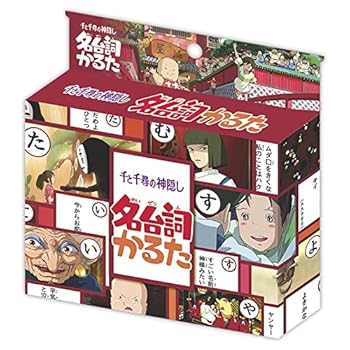冬は垂直にして光が地上に届くように
- 宇宙エレベータみたいな上空でもいい。もし日本全土を覆うような「巨大な屋根型ソーラーパネル構想」を実現できれば、エネルギー自給率を劇的に高める可能性があります。ただ、現実的には課題も多いです。
想定される利点
- エネルギー供給の安定化:全国規模で太陽光を集められれば、天候の地域差を平均化できる。
- ヒートアイランド対策:屋根状に覆えば直射日光を遮り、都市部の気温上昇を和らげる。
- 洪水・台風時の保護:強化構造なら建物や農作物も守れる。
主な課題
- コストと維持管理:資材・設置・補修費が天文学的規模になる。
- 環境・景観への影響:生態系や航空路への配慮が必要。
- 発電効率と蓄電問題:昼夜・季節差に応じたエネルギー貯蔵の仕組みが必須。
- 技術的難易度:上空構造の場合は宇宙エレベータ構想並みの素材強度が必要。
もっと現実的な方向としては、
- 自動角度調節機能を備えた地域単位の「可動型ソーラールーフ」
- 高高度気球やドローン型太陽光発電ステーション
- 都市ごとの「空中屋根型」防災兼発電ドーム
など、段階的な導入が考えられます。
人的被害が起きにくい農地から始めるのが現実的。ノウハウが集まったら都市に展開
- 農地から始めることで、安全確保と実証実験の両立ができます。
初期段階(農地での導入)
- 屋根型ソーラーパネル+アグリソーラー(営農型発電):作物上空に高架構造を設置し、日射量を調整しながら発電。
- 自動角度制御:季節ごとにパネル角度を変えて、冬は太陽光を地表に反射、夏は遮蔽。
- 災害対応構造:台風・降雪に耐える折り畳みや沈降モードを備える設計。
次の段階(都市部への展開)
- 駐車場・道路上空への拡張:交通機能を妨げずに発電と雨除けを両立。
- 公共施設屋上や駅コンコース:発電と防暑・防災を兼ねた社会インフラ化。
- 街区単位の「共用電力ドーム」:小規模スマートグリッドでエネルギー共有。
この手法なら、農地での実証データをもとに設計を最適化し、都市に応用する際のリスクを最小化できます。
2025年10月18日 「資源国に頭を下げる」政策に終止符を 高市氏が考えるエネルギー論
- 毎日新聞(2025年10月18日配信)による高市早苗氏のインタビュー記事「『資源国に頭を下げる』政策に終止符を 高市氏が考えるエネルギー論」は、彼女の総裁選公約およびエネルギー戦略を中心にした内容である。
高市早苗氏の主張の概要
- 高市氏は、日本が化石燃料をほぼ全量輸入に依存する現状を「資源国に頭を下げる外交」と表現し、その構造を改める必要があると強調した。
- 彼女は「国内エネルギー自給率100%」を目標に掲げ、エネルギーの国内生産強化を国家戦略として位置づけている。
政策方針
- 原発再稼働と次世代炉開発
安全面を確保したうえで既存の原子力発電所を再稼働し、将来的には「革新軽水炉」などの次世代原発へ移行する方針を示した。 - 核融合研究の加速
2030年代に核融合炉の稼働を目指し、研究開発に国家規模の投資を行う意向を示した。 - 産業政策との一体化
エネルギーと産業を一体で捉え、製造業を支えるために「安価で安定した電力供給体制」を重視している。「超円高時代に海外に出た企業の国内回帰」を促す狙いもある。 - 背景と視点
記事によると、電力消費は生成AIの普及などで世界的に拡大しており、高市氏はこの新たな電力需要増に応える国内エネルギー供給体制の強化を訴えている。産業界からは「核融合に前向きで日本の成長に希望を感じる」との声もある一方、「2030年代での核融合商用化は非現実的」との批判もある。
要するに、高市氏は原発と次世代技術を軸に「資源輸入依存から自立したエネルギー国家」を目指す構想を掲げている。