自分でどうにもできない問題について悩むことには意味がなく、時間の無駄である
古代史で最も有名な人物「卑弥呼」はなぜ古代史の記述が残る「日本書紀」「古事記」に登場しないのか?
古代史で最も有名な人物のひとりである卑弥呼が、『日本書紀』や『古事記』に登場しない理由は複数あります。最大の理由は、これらの歴史書が大和政権(ヤマト王権)の歴史を中心に編纂されたものであるのに対し、卑弥呼が支配した邪馬台国が、その勢力範囲外であった可能性が高いからです。邪馬台国が北部九州にあったならば、大和政権とほぼ無関係だったため『記・紀』には登場しないと考えられます。一方、もし邪馬台国が畿内にあったとしても、その関係が記録されていないのは大きな謎です。
また、卑弥呼は「卑弥呼」という固有名詞ではなく、「日の巫女」や祭祀を行う巫女的地位をあらわす普通名詞、すなわち役職名だったという説もあります。この場合、『記・紀』に卑弥呼が直接登場しないのも不思議ではありません。
さらに、『記・紀』に登場する女性たち(神功皇后や天照大神など)が、卑弥呼の特徴を投影した存在であるという説もありますが、決定的な証拠はありません。
また、卑弥呼を祭る神社や伝承も日本にはほとんど見られず、これは「記・紀」が編纂された時代の権力者側の政治的・宗教的な事情や、異端視されていた可能性も影響していると指摘されています。
つまり、卑弥呼が『日本書紀』『古事記』に登場しないのは、編纂の政治的背景や地理的・文化的な違い、そして名前や役割の捉え方の問題が複合しているためで、今なお歴史の謎として解明が進められている状況です。
大和政権と邪馬台国
大和政権と邪馬台国の関係については、歴史学界や考古学界で様々な説があり、はっきりとした結論は出ていません。主に以下の二説が議論されています。
- 邪馬台国大和説(連続説)
邪馬台国が奈良県の大和地方にあり、そのまま大和政権(ヤマト王権)に繋がったという説です。この説では、邪馬台国と大和政権は同一勢力の連続とみなされるため、卑弥呼の政治的資産がそのままヤマト王権成立の基盤となったとされます。纒向遺跡などの考古学的発掘がこの説を支持し、卑弥呼の墓とされる箸墓古墳もこの地に存在するという見方があります。 - 東遷説(移動説)
邪馬台国は当初九州北部に存在し、その後、卑弥呼の死後や邪馬台国連合の崩壊を経て、勢力が近畿地方に移り、そこで大和政権が成立したという説です。この説は魏志倭人伝の距離表記や地理的根拠を元に展開されており、九州の邪馬台国勢力が東へ移動し、近畿の豪族連合を吸収・支配して大和政権となったとされます。
また、「投馬国」という九州の国名と、後に近畿地方で台与の衛兵らが武装集団としてヤマト王権に従ったとする説もあり、邪馬台国の勢力と大和政権との間には一定の交流や繋がりがあった可能性も指摘されています。
要するに、邪馬台国と大和政権は連続的に関係していた可能性はあるものの、九州説と大和説の対立、そして移動説の存在により、両者の関係はまだ完全に解明されていません
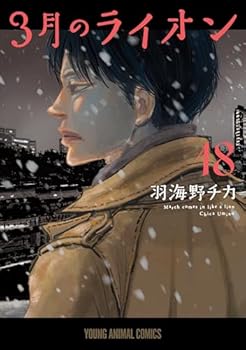
コメント