2025年10月15日 コメの作付面積は大規模化が進んでいる
コメ増産“宝の山”価格2倍…収穫量過去最大 大規模化進む中、手放す農家の複雑胸中
2025年のコメ収穫量は昨年より68万トン増で、747万7千トンと9年ぶりの高水準となりました。作付面積も10.8万ヘクタール増えて136万7千ヘクタールとなり、大規模化が進んでいます(「令和7年産⽔稲の作付⾯積及び9⽉25⽇現在の予想収穫量」)。
しかし価格が高止まりしている理由は複雑で、農家への概算金の上昇や流通業者間での争奪戦、品質問題からの不安感が影響しています。結果として、倉庫にコメがあふれていても価格は簡単に下がらず、農家間でも価格の折り合いがつかない状況が続いています。
また、高齢化で若い農家が減少しており、関さんのように大規模化を進める農家もいれば、病気などでコメ作りを手放す農家もいる状態です。平均年齢は80歳に迫り、農業の大規模化や効率化が急務となっています。
コメ収穫量増 なぜ価格は高止まり
コメの収穫量が増加しているにもかかわらず価格が高止まりしている背景には、いくつかの要因があります。
- 農協が農家からコメを買い取る際に支払う「概算金」の上昇により、流通段階での価格が押し上げられている。
- 2023年の猛暑などによる品質低下で加工用米の生産が減り、流通可能なコメの実質的な量が減少したこと。
- コロナ禍の収束に伴う外食需要の回復や在留外国人の増加による需要の急増。
- 品薄や価格高騰への不安感からの買い占め傾向や争奪戦が続き、価格が下がりにくい状況になっている。
- 政府の備蓄米放出など対策が行われているものの市場の不透明感や政策に対する不信感が残っている。
これらの複合的要因によって、供給量が増えても価格は簡単に下がらず、高止まりの状態が続いています。特に流通の仕組みと需給のアンバランス、品質の問題、そして消費者や業界の心理的な要素が価格に大きく影響しています
20年以上前から言われていた事です
コメ農家、「年収1000万円」で若者つなぐ 高齢化で危機感
日本のコメ農家では高齢化と担い手不足が深刻な課題となっており、特に個人経営の小規模農家では高齢者が多く、所得も非常に低い現状があります。2022年のデータでは、個人の米農家の年間平均農業所得はわずか1万円、時給換算で約10円という厳しい状況です。
こうした中、若者を農業に呼び込むため「年収1000万円」を目標とする農業法人の取り組みが注目されています。埼玉県加須市の中森農産のように、後継者のいない農家の事業を承継して規模拡大を図り、効率化やIT活用によって高収入を目指す事例が現れています。中森農産では、平均年齢30歳ほどの若いスタッフが多く、AIや自動運転トラクターなど最新技術を導入し、作業効率を高めることで「年収1000万円」を現実的な目標に掲げています。
このような高収入モデルの実現には大規模経営とビジネスモデルの刷新が不可欠です。例えば、100ヘクタール、200ヘクタールといった大規模な農地を管理し、法人化による効率的な運営やコスト削減を進めることが求められます。実際、規模の大きい農業法人では若い世代の雇用が進み、安定した収入を得やすい環境が整いつつあります。
一方で、小規模な個人農家では依然として高齢化と低収入が課題であり、耕作放棄地の増加にもつながっています。農地の有効活用と人材確保の両立が、今後のコメ産地維持のカギとされています。
まとめると、「年収1000万円」を掲げる農業法人の増加は、若者の新規参入を促し、コメ産地の持続可能性を高める重要な動きです。ただし、その実現には大規模化・法人化・技術革新が不可欠であり、従来型の小規模農家とは大きな格差が生まれているのが現状です。

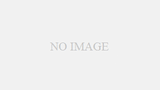
コメント