日中関係で日本の「対話重視」「波風を立てない」外交が裏目に出た
指摘の通り、この20年の日本外交は中国との関係で明確な方針を打ち出せず、情勢に応じて対応を変える「試行錯誤」の連続でした。特に習近平体制の長期化により、中国の対外姿勢が強硬化する中で、日本側の「対話重視」「波風を立てない」外交が裏目に出た部分も多いと分析されます。
中国の尖閣諸島周辺での公船侵入、領空侵犯に近い行為、経済報復など、従来の「経済協力で安定を保つ」構図はすでに崩壊しています。それにもかかわらず、日本が明確な報復措置や法的対応を取れなかったのは、国内に根強く存在する親中派の影響、経済依存、そして中国への過剰な配慮によるものでしょう。
公明党をはじめとする「中国パイプ」頼みの姿勢も有効に機能していません。拘束された日本人の解放交渉にしても、政治的圧力として機能していない点を見ると、信頼関係というよりも一方的な譲歩構造が定着しています。実際には「距離を取った現実的な関係」に立ち戻る方が、日本の主権を守るうえで合理的です。
また、中国との関係を優先するあまり、与党内部にまで「事なかれ主義」や「左傾化」の流れが生じ、外交安全保障の原点が曖昧になっている点も問題です。結果として、日本の外交自主性や抑止力が低下し、地域全体のバランスを崩しているといえます。
今後の方向性としては、経済依存の分散化、サプライチェーンの脱中国化、防衛力の強化、価値観を共有する民主主義国家との連携拡大が必要です。中国を過度に敵視せずとも、対等な立場を維持するためには「対中迎合ではなく現実主義的防衛外交」への転換が求められています。
2025年10月09日 [深層NEWS]公明党が連立離脱なら「中国との距離はさらに遠く」…東京財団・柯隆主席研究員
BS日テレ「深層NEWS」に出演した東京財団の柯隆主席研究員と東京大学の阿古智子教授が、日中関係の現状と影響要因について議論した内容をまとめたものです。
柯氏は、自民党の役員人事で中国とのパイプ役だった森山裕氏が幹事長を外れたことで、中国が直接話せる相手がいなくなったと指摘し、さらに公明党がもし連立を離脱すれば、中国との距離は一層遠くなるとの見方を示しました。
阿古氏は、高市総裁が対中強硬姿勢を示す場合、それが中国側に政治的に利用されないよう、発言や行動を十分に見極めながら進めるべきだと述べました。
「対中強硬姿勢が中国側に利用される」とは
具体的に日本が中国に対して強硬な態度や発言を取る場合に、それが中国の対日政策や外交戦略の中で巧みに利用されてしまう可能性を指します。
この意味は以下のように解釈できます。
- 強硬姿勢を示すことで、中国側がそれを「日本の攻撃的・敵対的な態度」として宣伝や国内向けのナショナリズム強化に使い、対日世論を固めたり、国際舞台での優位を図る材料にするケース。
- 強硬な態度により中国国内や国際社会に「日本の脅威」をアピールし、それを根拠に自国の軍備増強や外交圧力の正当化に転用する。
- 日本の強硬発言が中国側の一方的な反発を助長し、かえって対話の余地を狭め、関係改善や交渉の土台を崩す結果になる恐れ。
つまり、強硬姿勢が必ずしも日本の立場を強めるとは限らず、逆に中国のプロパガンダや戦略的計算に資することもあるため、その発言や行動を慎重に見極める必要があるということです。
阿古氏のコメントは、そのような観点から高市総裁に対して、中国側に利用されないように注意深く対応すべきだと助言したものと解釈されます。
これまで注意深く対応したが得るものは無かった
2025年の状況を見ると、中国の軍用機や海警船による日本の領空・領海侵犯は依然として頻繁に発生しています。例えば、防衛省発表によると、中国機に対しての緊急発進回数は2025年1四半期だけで約1300回以上、中国海警船は尖閣諸島周辺の領海に連続して侵入し、2025年5月3日にはヘリコプターが領空を侵犯する事例もありました。
尖閣諸島周辺では、中国海警船が260日以上連続して接続水域や領海に航行し、領海侵入を繰り返している状況です。これらの動きに対し、警戒や抗議を続けていますが、頻発していることから「過去の慎重な対応が必ずしも抑止につながっていない」という事実が示されています。
このことから、日本周辺の安全保障環境は厳しさを増し、フィリピンやベトナムのように中国に対して毅然とした対応を強めるべきとの議論があることも理解できます。
東京財団の柯隆主席研究員
東京財団政策研究所の柯隆(か りゅう)主席研究員は、1963年に中国の南京市で生まれ、1988年に来日。愛知大学法経学部を卒業後、名古屋大学大学院経済学研究科修士課程を修了し、経済学修士号を取得しています。長銀総合研究所や富士通総研経済研究所で主任研究員、主席研究員を務めた後、2018年から東京財団政策研究所の主席研究員に就任しています。
研究分野は開発経済、中国のマクロ経済に特化しており、著書に『中国「強国復権」の条件』『ネオ・チャイナリスク研究』『中国の統治能力』などがあります。また、静岡県立大学グローバル地域センター特任教授や広島経済大学特別客員教授も兼務しています。日本語・英語に堪能で、日本語検定1級やケンブリッジ大学ESOL試験などの資格も持っています。
彼は特に中国経済の課題や国際金融システムへの影響、日中関係について幅広く研究・発信しているエコノミストです。
- 日本の人口減少と高齢化がもたらす経済への影響を膨大なデータに基づいて明快に分析し、これから確実に起こる日本経済の変化を示す著作です。著者は、人口減少による労働力不足や賃金の上昇、人手不足によるサービスの質変化、緩やかなインフレーションの定着といった5つの主要な変化を通じて、日本社会と経済の新しい局面を予測しています。個人としてはスキルアップや柔軟な働き方、消費行動の見直しなどの対応を促しています。
主な内容は以下の通りです。
人口減少と高齢化の影響
- 2007年のピークを境に人口減少が進み、労働力も購買力も減少する
- 地域別に高齢化が進み、都市部と地方で課題が異なる
労働市場の変化
- 労働力不足が深刻になり、企業は賃金を引き上げざるを得ない
- 高齢者や外国人労働者の活用が必要だが限界もある
賃金の上昇傾向
- 2012~2023年で名目時給は12.2%上昇
- 特に地方や飲食宿泊業で顕著に増加
サービスの質変化
- 「高品質・低価格」サービスの見直しが進む
- 再配達有料化やセルフサービス化が広がる
インフレーションの定着
- 賃金上昇による物価のゆるやかな上昇が始まる
- 企業は生産性向上や新技術の導入を急務とする
これらの未来予測に対し、著者は個人や社会が積極的に変化に適応し、新しい価値観を取り入れてゆく重要性を説いています。
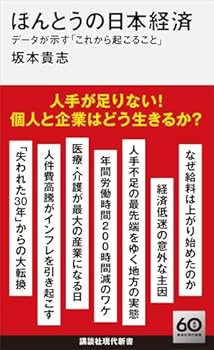
コメント