ライドヘイリング
ライドヘイリング(Ride-hailing)とは、スマートフォンアプリを使って、一般ドライバーの自家用車やタクシー車両を呼び出し、目的地まで送迎してもらうサービス全般を指します(例:Uber、Lyft)。これは「ライドシェア(相乗り)」と混同されがちですが、ライドヘイリングは「呼び止める(hail)」という要素が強く、乗客が車両を呼び出して乗る形態で、相乗りではない場合が多いのが特徴です。日本では近年、タクシー会社と連携した「日本版ライドシェア」として、自家用車を使った有償サービスが解禁され、都市交通の新たな選択肢となっています。
2025年12月23日 【シンガポール】新規配車サービス2社、正式な事業免許取得
- シンガポール陸上交通庁(LTA)は、ジオ・ラー(Geo Lah)とトランスキャブ・サービシズ(Trans-Cab)に正式な配車サービス事業者免許(RSOL)を付与し、国内の免許保有企業が7社となった。
免許取得の経緯
- 両社は2024年12月に仮免許を取得し、2025年1月1日から1年間有効だった。 LTAは、安全基準とサービス基準を満たした運営能力を認め、2025年12月22日から正式免許へ移行した。 有効期間は2027年末までで、800台以上の車両を運用する事業者に義務付けられる。
対象企業概要
- ジオ・ラーはアプリ「Geolah」を展開し、2025年にライドヘイリングを開始、プロモーションとして2026年までドライバー手数料を免除する。 トランスキャブはタクシー大手で「Smile Ride」アプリを導入、2,200人のタクシー運転手と300人のプライベートカー運転手を擁する。
国内全7社一覧
- CDG Zig(Zig)
- GrabCar
- Ryde(Ride Technologies)
- Tada Mobility
- Velox Digital Singapore(Gojek)
- Geo Lah
- Trans-Cab
この決定により、シンガポールのライドヘイリング選択肢が増え、競争が活発化する見込みだ。
日本のタクシー業界との比較
- シンガポールのタクシー・配車サービスはアプリ中心で多様な選択肢があり、日本より柔軟だが料金変動が課題だ。日本はタクシーの信頼性が高い一方、配車アプリの普及が遅れている。
利便性の比較
- シンガポールはGrabやGojekなどのアプリで即時配車が可能で、24時間利用でき、キャッシュレス決済が標準。待ち時間が短く、英語対応もスムーズだ。日本は街頭タクシーが多く、GOなどのアプリがあるが、都市部以外で配車しにくく、深夜料金追加が目立つ。
経済面の比較
- シンガポールは基本料金が安く(初乗り約100円相当)、短距離で日本より2-3割安いが、サージ料金(ピーク時倍増)で高騰しやすい。日本はメーター制で料金が安定し、初乗り410円前後だが、長距離や深夜で割高になる場合がある。
| 項目 | シンガポール | 日本 |
|---|---|---|
| メリット | 安価・アプリ多・直行便 | 安定料金・清潔・安全 |
| デメリット | 料金変動・混雑時高騰 | 高め・配車待ち・アプリ少 |
シンガポールと日本の満足度
- シンガポールのタクシー・配車サービスはアプリの利便性と安価さが評価され、利用者満足度が高い。日本は清潔さと安定性が強みだが、アプリ普及の遅れが不満点だ。
シンガポールの満足度
- GrabやGojekなどのアプリが普及し、待ち時間短縮とキャッシュレス決済で高評価。安全性が高く、料金の透明性も支持を集め、旅行者満足度は90%以上と推定される。ピーク時のサージ料金が唯一の不満。
日本の満足度
- メーター制の信頼性とドライバーの礼儀正しさが世界トップクラスで、満足度は95%超。都市部では清潔で安全だが、地方や深夜の配車難が課題。
比較表
| 項目 | シンガポール満足度 | 日本満足度 |
|---|---|---|
| 利便性 | 高(アプリ多) | 中(街頭中心) |
| 料金安定 | 中(変動あり) | 高(固定) |
| 安全性 | 高 | 最高 |
| 全体評価 | 4.5/5 | 4.7/5 |
中国でタクシーの過剰供給・収入減少
- タクシー余りすぎ!ライドシェアの影響でタクシーが過剰に。料金自由化に踏み込む都市も
中国におけるタクシー業界の現状は、ライドシェアの急速な普及によりタクシー利用が大幅に減少し、タクシーが余る過剰供給の状態に陥っている。特に駅、空港、ショッピングモールといった場所では、長いタクシーの客待ち行列が頻繁に見られる一方で、多くの利用者はスマートフォンでライドシェアを呼び、タクシーを避ける傾向にある。
過剰供給の原因は、ライドシェアの登場で規制緩和が進み、タクシー車両数が増加したことに加え、不況の影響でタクシー運転手のなり手も増えたためである。これにより、2024年下半期の広州市のタクシー乗務回数は前年から11.74%減少し、1台あたりの売上も8.82%減少している。深圳市でも同様の傾向が見られ、運転手の収入減少も深刻だ。
対応策としては、一部の地方都市(昆明、長春、鄭州、合肥など)でタクシー料金の自由化が進んでおり、最大30%の割引も可能となっている。これはライドシェアに対抗し、乗客を取り戻すための施策であるが、割引が常態化すると運転手の収入減少やタクシー会社の経営悪化を招く恐れがあり、業界再編の前兆と見られている。
日本の状況を対比すると、ライドシェア導入に期待しつつも、タクシー業界の運転手不足が課題となっており、ライドシェアはタクシー不足解消の一助と見られているものの、供給と需要の調整や安全・サービス品質の問題も残されている。料金自由化や規制緩和の動きは中国同様見られるが、地域差や需給バランスの難しさが継続的課題である。
まとめると、中国ではライドシェアの普及がタクシー需要を大きく減少させ、タクシーの過剰供給・収入減少問題を引き起こしている。それに対して料金自由化を進める都市もあるが、業界全体の再編リスクを孕んでいる状況である。日本ではまだライドシェアの本格普及は限定的で、タクシー不足問題と供給調整が主な論点となっている。
ライドシェア 2014年性的暴行 2018年乗客殺害
河野大臣だけではなく、自由な競争と規制改革を強く主張してきた菅義偉(よしひで)前首相や小泉進次郎元環境相も、ライドシェアの導入を度々訴えてきた。しかし、ライドシェア導入に慎重な意見が根強いのは、ライドシェアを導入したアジア各地ではさまざまな問題が生じているからだ。例えば、2014年にはインドのデリーでウーバーの運転手が乗客を性的暴行したとして逮捕され、同社は営業停止に追い込まれている。一方、2018年には中国で滴滴出行(DiDi Chuxing)のドライバーによる乗客殺害が続き、同社はドライバーに対する徹底的な調査などの改善措置を迫られた。
ライドシェア推進派は、タクシー業界が「既得権益」を守ろうとしていると反論する。しかし、推進派がライドシェア導入の議論を急ぐ背景にも、「新たな利権」があるのではないかとの声も出てきている。
河野デジタル大臣が「ライドシェア導入」の旗を必死に振り続けるワケ
Grabの説明
12分56秒より
著者は「衝動」を幽霊のようなものにたとえ、自分でもコントロールできない情熱や欲求が心の中に潜んでいると説明しています。こうした衝動は理屈や効率とは対極にあり、自分の心の叫びに耳を澄ますことで初めて見つけられるものです。衝動は人によって異なり、外部環境の変化や人生の岐路において、自分の内なる欲望が表面化し、人生のレールから脱線する力を持っています。
また、本書は「偏愛」と呼ばれる個人的でミクロな欲望に注目し、そこから衝動を掘り起こす方法も紹介しています。偏愛とは何気ない日常の中で現れ、表面的にドラマティックでないため気づきにくいモチベーションのことです。著者は、そうした細かな欲求に敏感になるセルフインタビュー的な実践を推奨しており、衝動を発見し、その熱を仕事や人生に活かすヒントを与えています。
特に、安定した人生のレールに乗ることが必ずしも幸せとは限らず、むしろ衝動を観察し理解することで、自分固有の生き方ややりたいことが見えてくると説いています。この本は自己啓発書のような単なるモチベーション向上とは違い、哲学的考察と具体的な実践法を融合した珍しい内容となっています。
簡単に言えば、『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』は
- 人生の「普通の道」から外れる強い衝動を、心の声として探し出す方法
- その衝動は理屈を超えた情熱であり、自分の偏った「好き」を掘り下げることで見つかる
- 衝動を理解し活かすことで、より自分らしい人生や働き方が可能になる
という内容の本です。

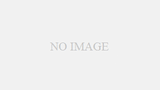
コメント