- エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ 自発的隷従論
- 人生を破壊する習慣 なぜ無気力になるのか 少数者が勝つゲーム
- 1つ目「権力に対する不審感」
- 2つ目「人文主義の影響」
- 1つ目のテーマ「人生を破壊する習慣」
- 圧政を支えるのは民衆の服従である
- 2つ目のテーマ「なぜ無気力になるのか」
- 3つ目のテーマ「世襲によって支配を受け継いだもの」
- アベノミクスにより世界5位から30位に転落した
- アベノミクスでトリクルダウンが起きなかった理由
- 儲からない製造業を推したことが原因?
- アベノミクス偽装 研究開発費など加え GDPかさ上げ
- 日本のギリシャ化=観光国化
- 失業率改善は「団塊世代の退職で労働人口不足」なだけ
- 労働者派遣事業をなくせば、手取りは今の3割は騰がるだろ
- 楽天・三木谷氏「移民政策以外に手はない」
- 日本企業が欲しいのは奴隷だけ
- そもそも優秀な人材は日本を選ばない
- 30年も発展しない国
- 観光しか売るものがなくなった国
- 「工業技術の時代」の終焉…次は「情報技術の時代」
- 中国とアメリカのデカップリングで世界が変わった
- “6つの未来” あなたはどれを選ぶ?
エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ 自発的隷従論
今から約500年前、1人の青年が人間社会の支配構造を暴き世界を震撼させました。彼の名はエティエンヌ・ド・ラ・ボエシ。フランスの若き天才法学者です。代表作、自発的隷従論を紹介します。特に世の中の不条理について疑問を抱いている方、人間社会の構造を深く理解したい方、人の意見や場の空気に流されやすい方、自由な生き方を模索している方に是非手に取っていただきたい1冊です。
人生を破壊する習慣 なぜ無気力になるのか 少数者が勝つゲーム
本書が問うのは人間社会の奇妙な構造、すなわちなぜこの世界は大数の民衆が少数の支配者に服従しているのかという問題です。これにボエシは驚くべき答えを示します。人々は無理やり支配されているのではない。むしろ自ら進んで奴隷状態に陥っている。日に日に生活が苦しくなり生きづらさが増していく現代社会。今回の動画では本性を紐も解きながらその状況を打開するヒントを探ります。まずはこの動画の全体像からお示しいたします。初めに背景知識として著者について簡単に紹介しその後本書の内容を
- 人生を破壊する習慣
- なぜ無気力になるのか
- 少数者が勝つゲーム
という3つのテーマに沿って進めてまいります。
ド・ラ・ボエシ。彼は1530年フランス南西部の小さな町サルラで誕生しました。地方貴族という恵まれた家計でしたが生後間もなく両親が他界し聖職者の叔父に引き取られました。そこで神学や古典の手ほどきを受けたボエシはフランスの名門オルレアン大学に進学。法学哲学文献学などを納め23歳の時に法学士号を取得。同時期に代表作「自発的隷従論」を書き上げます。卒業後は高い学が評価されボルド高等法の標定官に就任。そこで生涯の友となるミシェル・ド・モンテーニュと出会います。彼の代表作には2人の友情がいかに純粋で揺ぎないものであったかが綴られています。私たちは意思・思想・判断、全てが共通であったアリストテレスの適切な定義に従えば私たちは身は2つ心は1つであり、何かを貸し合うことも与え合うこともありえない。しかし1563年ボエシは突然病に倒れます。原因は伝染病の1つ赤痢。また当時猛威を振っていたペストだったと言われています。彼は日に日に衰弱していき、ついに見取られながら静かに息を引き取ります。33歳、あまりに短い生涯でした。自発的隷従論が書かれた背景には大きく2つの要因があると言われています。
1つ目「権力に対する不審感」
ボエシが生きた16世紀フランスは民衆と国家権力との間に大きな亀裂が生じた時代でした。そのきっかけとなったのがズバリ税金です。当時フランスにはガベルという課税がありました。ガベルは元々消費税を意味していましたが15世紀以降は塩に貸される塩税を指すようになりました。塩は日々の暮らしに欠かせない必需品でありながら大塩税地方、小塩税地方というように地域によって税率が異なるという問題があり、塩税はしばしば悪税の象徴とされていました。そんな中ついに民衆の不満が爆発。不公平な税制の撤廃を求め大規模な反乱が起こります。しかし王権側はその声を聞き入れるどころか武力によって鎮圧。歴史家のジャック・オーギュストは権力が暴走したこの事件を本書が書かれた1つの要因と指摘しています。
2つ目「人文主義の影響」
ボエシが学んだオルレアン大学はルネサンスの知的拠点であり人間の尊厳と自由を重んじる人文主義の中心地でもありました。こうした環境の中で彼は伝統的な権威に疑問を持ち社会のあり方を問い直そうとしたのかもしれません。自発的例論は支配と複住の構造に鋭く切り込んだ作品でありフランス革命期には絶対的な権威に抗がう理論的支柱として利用されました。しかしボエシには革命を扇動する意図はなく、また親友の門弟にも本作が政治的扇動の書と誤解されることを懸念し彼の死後も公表をためらったと言われています。ボエシが目指したのは既存の政治体制の破壊ではなく人類の歴史の中で繰り返されてきた独裁的権力に対する批判的考察でした。その内容は時代を超えても色あせることなく現代に生きる私たちにも重要示唆を与えてくれます。なぜ人は自ら権力に服従してしまうのか。今回の動画ではが明かした自発的隷従のメカニズムと人間の本性に迫ります。
1つ目のテーマ「人生を破壊する習慣」
カエサル・ナポレオン・ヒトラー・スターリン。歴史に直刻んだ支配者は一体どのようにして圧倒的な権力を手にしそれを維持してきたのでしょうか?強大な軍事力。厳格な監視体制。絶対的な法の支配。それだけではありません。ボエシはむしろ民衆が自ら進んで服従していることが権力の礎になっていると指摘します。自分の自由を放棄してまで長いものに巻かれ、強いものに折れ、重いものに押されたがる人間の性質をボエシは「自発的隷従」と名付けました。ではなぜ人は自ら服従してしまうのか?本書ではその根本的な原因として習慣を上げています。例えば国家の危機を救った英雄が民衆からの熱狂的な支持を得て国王に推挙されたとします。当初は国民の生活を第1に考えた統地を行っていましたが、次第に贅沢に溺れ、強欲な独裁者へと変貌してしまいます。さてこの時国民は彼の異変に気づき批判したり抵抗したりできるでしょうか?ボエシの考えに従えば今まで通り人々はその威光と権力の前にひれふすことになります。なぜなら長い間服従を続けた結果、服従するという生活自体に慣れてしまったからです。古代ポントス王国の王ミトリダテス6世。彼は毒殺を恐れるあまり自ら少量の毒を飲み続けることで耐性をつけたと言われています。ボエシはこれに名ぞらえ圧政のもとで隷従を続けることはまさに毒に慣れる行為だと警告します。最初は苦痛に感じた服従も、繰り返されるうちに違和感がなくなり、やがて当たり前のものとして受け入れてしまうのです。習慣は第2の天性とも言うように、それは生まれ持った資質や才能も容易に塗り換える力を持っています。例えばどれほど健康な体に恵まれていてもいつもストレスにさらされ偏った食生活を続けていればやがて体調を崩し不健康な体になってしまいます。生まれつきの性質はいわば自然の産物であり、環境や習慣次第で良くも悪くも変化するのです。したがって支配的な状況から逃れるためには何よりもまず隷従という毒を飲む習慣をやめるしかありません。その上でボエシは次のように語ります。「たった1人の圧政者に立ち向かう必要はない。打ち倒す必要もない。ただ隷従することに合意さえしなければ、そのものは自ら破滅するだろう。何かを奪う必要もない。ただ何も与えなければ良いのだ。炎は小さな火から発し、薪をくべるほど大きくなる。もし炎を消したければ水を与えるまでもない。薪を与えなければいい。燃やすものがなければそれは自然と小さくなりついには消えてしまうのだ。圧政者に服従すること。それは暑さに苦しみながら自ら炎に薪をくべるようなものだ。与えれば与えるほどより一層力を増し、破壊の限りを尽くすだろう。しかしそれでも民衆たちは隷従する自由という麗しい財産を放棄する。私にはその理由が分からない。民衆たちよ、あなた方は自分の財産のうちで一際は目を引くものが略奪されているのだ。自分の畑や住処が強奪されているのになぜ黙っている。なぜ見過ごしている。あなた方が身に粉にして働いてもそれは結局彼らが贅沢に耽り賤しい快楽に溺れるのを助けているだけだ。こんな卑劣な行いは獣でも耐えることはできない。もう隷従しないと決意せよ。そうすればあなた方は自由の身だ。敵を突き飛ばせ。振り落とせ。と言いたいのではない。ただこれ以上支えなければいいのだ。そうすればそのものは土台を奪われた虚像のごとく自らの重みによって崩落するであろう」。
圧政を支えるのは民衆の服従である
ボエシが強調するのは「圧政を支えるのは民衆の服従である」という点です。権力の乱用や不当な搾取が行われてもその状況を仕方がないと受け入れ習慣化してしまえば自ら支配体制を支えることになります。そこで彼は自由を取り戻すためには力で打倒するのではなくただ隷従をやめるだけでいいと解きます。この考え方は20世紀に展開されたガンジーの非暴力不服従運動とも重なります。彼もまた暴力に頼らず従わない姿勢を貫くことで権力の無効化を試みました。またボエシは人間だけでなく生きとし生けるものは生まれながらにして自由であると考えました。その観点から言えば支配や隷従は自然の設理に反するものと言えます。幼い時は誰もが本能的に親に従います。しかし大人になるにつれて理性が発達し「誰かが敷いたレールの上を歩きたくない」「自分を縛る習慣や枠組から外れたい」といった思いを強めていくものです。そのような意味で理性とは人間に自由をもたらす力と言えるでしょう。しかしその力は正しく育まれなければ十分に発揮されることはありません。あれをするなこれをするなと理性の成長を抑えつけるような環境・習慣にさらされていると、いつしか人は誰かに従うことが当たり前になり、自由という翼を失うのです。実はこうしたに隷従に関する議論は古くからあり、ボエシの主張は過去の理論と真っ向から対立するものになります。例えばローマ帝国時代の進学者アウグスティヌスは起源を原罪による意思の堕落に求めました。キリスト教ではアダムとイヴが神の意に背き禁断の果実を口にしたことを原罪と呼び、人類は皆生まれながらにして罪を背負っているとされます。こうした前提に立った上でアウグスティヌスは神が地上の平和を保つため意思の弱い人間を支配者に服従させるように定めたと主張しました。また古代ギリシャの哲学者アリストテレスも支配や隷属を自然なものとして解釈しました。彼はその根拠として自然界に階層という秩序が存在していることや、人間が家族・村・都市・国家といった共同体を形成する本性を持っていることを挙げています。しかしボエシはそれは何者かによって牙を抜かれ手懐けられているだけであって、本質的には人間も動物も皆自由なのだと古典的な見解を退けます。さらに彼は全ての人間は自然によって同じ形に作られており誰もが平等であると主張します。つまり支配するために生まれてきた人も支配されるために生まれてきた人も自然界には存在しないというわけです。しかし人間には学力・運動能力・芸術的才能など明らかに個体差があります。人間が皆平等ならばなぜ自然は私たちに均等に能力を授けなかったのでしょうか。ボエシはその理由を次のように語ります。自然はあるものには大きな分け前を与え、あるものには小さな分け前を与えた。それは私たちに兄弟愛を教えるためである。あるものが人を助ける力を発揮する時、あるものはそれを受け取る力を発揮する。このような状況の中で自然という母は兄弟が生まれることを望んだのである。
ボエシは人間の個体差は不平等や分断を促すものではなくむしろ兄弟愛・助け合いや支え合いを教えるものであると解きます。もっと頭のいい人間だったら。もっと美しい人に生まれていたら。私たちは時に与えられた教遇に不満を抱きます。しかし本質的な問題は個体差というよりその違いが上下関係や支配関係に転じやすいという点にあります。古の格言にあるように、大いなる力には大いなる責任が伴います。人よりも恵まれた支質や力があるということは、それを誰のためにどのように生かすかが問われているということです。ただしそれは持つものが持たざるものよりも上位の存在であることを意味するわけではありません。例えばどんなに歌の才能があっても、誰にもその声を聞いてもらえなければその人物は自分の存在価値や生きる喜びを見失ってしまうかもしれません。つまり両者は役割が違うだけであくまで対等であり互いに支え合って生きているのです。では持たざるものの役割とは何でしょうか?それは与えられたものを受け取るということです。なんだそんな楽な仕事かそう思うかもしれません。しかしこれは単純なようで意外に難しいものです。例えば想像してみてください。自分が欲しいものを全て所有しているような人物から、やや耳の痛い有益なアドバイスをもらったとします。この時私たちはそれを素直に受け入れ自分の糧にできるでしょうか?もし相手に強い嫉妬や憎しみを抱いていたら。もし自分の心の中に卑屈な感情があったとしたら。もしその助言が自分の弱点を鋭くつきまるで見透かされたかのように感じたとしたら。果たしてどれだけの人が感謝の気持ちを持って自分を卑下することなくそれを受け取ることができるでしょうか。余計なプライドが邪魔をしてせっかくのチャンスや施しを無駄にしてしまう人は少なくありません。しかし本来与える側と受け取る側はどちらが上でも下でもなく、異なる役割を担っているだけなのです。持つものは奢らず。持たざるものは卑屈ならず。互いに対等な存在として手を取り合えるのか。母なる自然は両者に異なる試練を課すことで人類の間に兄弟愛が生まれることを望んだのかもしれません。次のパートでは圧政者がどのようにして支配構造を築づき、それを維持しているのかという具体的な手口に迫ります
2つ目のテーマ「なぜ無気力になるのか」
本書によれば圧政者には大きく3つのタイプがあると言います。1つは民衆の選挙によって選ばれたもの。こちらは一見国民の味方のように思えますが権力を手にするとその地位に固執し民衆を従順な家畜のように扱う傾向があります。もう1つは武力によって権力を奪い取ったもの。彼は征服者として振る舞い国民を自分が手に入れた獲物とみなします。
3つ目のテーマ「世襲によって支配を受け継いだもの」
彼は生まれながらの独裁者であり国民を父や祖父から受け継いだ「所有物」あるいは「奴隷」と考えます。ボエシはこのように圧政者のタイプを整理した上で、結局どんな人間も大きな権力を手にすると支配的になっていく傾向があると指摘します。ではこうした事態を未然に防ぐにはどうすれば良いのでしょうか?それは1人の人物に長期間にわたって権力を集中させないことです。特定の個人が何十年にもわたって強い力を持ち続けると、その人物に従うことや逆らわないことが人々の間で習慣化されていきます。それはすなわち隷属という毒を飲ませ、服従を自然なものとして受け入れさせる、ある種の教育と言えるでしょう。ボエシはその危険性を次のように訴えます。生まれながらにして隷従しているものはこう語るだろう。「自分たちはずっと彼に従ってきた。祖父の代からそうやって生きてきた」と。だがそれは単にそう思い込まされているに過ぎない。こうやって自らの手で長い時間をかけて圧政者を支えているのだ。年月は悪い行いに正当性を与えない。かえって不正を募らせるものである。
つまり圧政が維持される背景にはこれまでずっとそうだったという理由だけで今の状況を疑わずに受け入れてしまう、いわゆる現状維持バイアスがあるというわけです。そこから抜け出すには自分を俯瞰する能力が必要であり、それは一般的に書物や教育によって養われます。しかし歴史上の多くの独裁者は、人々が知の力によって目覚めることを恐れ、意図的に教育を制限したり、優秀な人間や知識人を排除したりしてきました。またボエシは自由を奪うことは同時に勇敢さを奪うことでもあると指摘し、その上で支配者が民衆を臆病にしておきたい理由を次のように語ります。
自由な者たちは共通の善のため、そして自らのために互いに切磋琢磨し高め合うものである。勝利の喜びも敗北の苦しみも分かち合いながら共に歩んでいく。しかしに慣れたものは戦う勇気を失うだけでなくあらゆる面で活力を失い、心は卑屈になり無気力に陥る。偉大なことを成し遂げようとする意思すら持てなくなるのだ。圧政者たちはこの心理を熟知している。そして民がこうした習慣に染まるのを確認するとさらに彼らを弱体化させる策を講じ、支配をより強固にするのである。
圧政者にとって最も厄介なのは支配下にいる民衆が反旗を翻すことです。そこで彼らは人々を臆病で無気力な存在にしておくためあらゆる手を尽くすと言います。では具体的にどのようにして民衆の力を弱体化させるのでしょうか。ボエシはその巧妙な手口を5つ上げています。
1つ目「娯楽で骨抜きにする」
かつてペルシア王キュロスはリディア王国を征服しました。その際彼は暴徒と課した民衆を軍事力ではなくなんと娯楽の力で抑え込みました。国王自ら「アルコール・ギャンブル・売春などを大いに利用すべし」と布告したのです。これによりリディアの人々は戦う意欲を削がれ、自然と隷従を受け入れてしまいます。キュロスは娯楽には相手にバレないように自由を奪う力があることを知っていたのです。
2つ目「口の支配」
古代ローマの独裁者たちは食料や見せ物を市民に気前よく提供することで支持の獲得と政治的無関心を促しました。これはパンサーカスという政治手法で代表的な愚民政策の1つです。またボエシは支配者たちが表向きには施しと言いながら実際には何も与えていないという実態を暴露しています。国民から高額な税を徴収し貧困に追い込んだ上で物資やサービスを与える。これは施しではなく奪ったものを一部返すことで恩を売るといういわゆるマッチポンプ商法のような手口と言えるでしょう。しかし多くの国民はこれに気づかず国王万歳と叫びさらなる支配を受け入れてしまうのです。
3つ目「偽りの称号」
ローマの皇帝は自らを護民官であると名乗ることで自分の支配を正当化しました。護民官とは平民の権利や財産などを守るために設置された官職のこと。一言で言えば庶民の味方です。そこで皇帝は護民官という称号を自らに与えることで「私は庶民の皆さんの味方なんです」と大々的にアピールしました。すると市民の間で「皇帝は庶民を守る立場であり、批判すべき相手ではない」という風潮が広がり、結果として皇帝の権力はますます強化されるのです。
4つ目「セルフプロデュース」
古代エジプトやアッシリアの王たちは自分自身を神聖な存在として演出することで民衆に畏敬の念を抱かせ絶対的な支配を確立していました。彼らは滅多に姿を見せないことでその存在を神秘化し、また姿を表す際には頭に火や動物を載せるなど神の化身であるかのように振る舞ったと言います。
5つ目「宗教心の利用」
ローマ皇帝ウェスパシアヌスは盲人の視力を回復させ足の不自由な人を歩かせたなど数々の奇跡を起こしたと伝えられています。しかしボエシはこうした話を間に受ける人々こそ本当の意味で盲目なのだと痛烈に批判します。なぜなら奇跡や伝説は古代から権力者が独裁を正当化するために使ってきた上等手段だからです。ローマの詩人ウェルギリウスのアエネイスに登場するサルモネウス王も人々の信仰を利用した典型的な人物です。彼は神ゼウスになりすまし松明を振りかざして雷を演出することで自らを神のごときであると装いました。しかしその傲慢さによってゼウスの怒りを買い、本物の雷で打ち砕かれることになります。その上でボエシは宗教と人々の純粋な信仰を利用した権力者は同じように罰を受けるべきだと訴えます。しかし1度築かれた支配体制はなかなか崩れないものです。一体なぜなのでしょうか?そこで次のパートでは民衆の他に圧政を支えているもう1つの柱に光を当てていきます。
3つ目のテーマ「少数者が勝つゲーム」
圧政を守っているのは騎馬隊でも歩兵団でも武器でもない。信じられないかもしれないが今から伝えることは事実である。すなわち圧政者をその地位に留めているのは常に4人から6人のものである。彼らは圧政者の信頼を得ると共に残虐な行為を行い、淫行のお膳立てをし、共に快楽を貪り、略奪した財宝のおこぼれに預かるのだ。さらにこの6人は甘い汁を吸う600人の部下を従え、同じような関係を築づく。そして600人の者たちはさらに6000人の部下を従え、土地や税金の管理に当たらせる。こうして6000人を欲深くし、必要とあらばさらなる悪事を行わせるのである。
何事においても少数よりも多数の方が有利だと言われます。しかしだとすればなぜ数で勝る民衆が少数の支配者に屈服してしまうのでしょうか?ボエシが問うのはまさにこの逆転現象なのです。そこで彼が注目したのが圧政者の周りにいる側と、彼らを中心に築き上げられる利権構造です。支配者は権力や富に飢える少数者におこぼれを分配。それを次々と下層へと流し、自分の体制に従った方が得をするという三角構造を作ります。これにより利権を享受するものがどんどん増え、結果として支配体制が盤石となるのです。またフランスの哲学者シモンヌベイユはこの逆転現象を次のように説明しています。多数者をまとめることはそもそも不可能である。結合しうるのはほんの少数の人々だけだ。つまりまとまっていない多数よりもまとまった少数の方が勝るというわけです。もちろんフランス革命のように大勢の人々が一致断結し少数の支配者を打倒するというケースもあります。しかしそれは一時的に断結しているだけであり、100年~200年と続くようなものではありません。さらに言えば支配者を追放しても多くの場合別の支配者がその場所に座るだけであり、支配と服従という構造自体が消えるわけではないのです。その上でボエシはこうした圧政のネットワークに加担することについて次のように語ります。「圧政者に尻尾を振り利益を得ようとする者たちを見るたびに、私はその悪辣さに呆きれる一方で、時よりその愚かさが哀れに思えてくる。なぜなら圧政者に近づくことは自ら自由を遠ざけ隷属を抱きしめることだからである」。邪な気持ちを捨て、貪欲さを抑え、自らの姿をありのままに見つめるがいい。そうすればあなた方が苦しめている市民はあなた方よりも幸福であり、自由であると気がつくはずだ。彼らは隷従しているが言われたことを守ればそれで済む。だがあなた方は常に支配者に媚びへらい、気を引いていなければならない。彼の快楽を自分の快楽とし、自分の本性を捨て去らなければならない。彼の言葉・声・視線に耐えず注意を払い、忖度しなければならない。果たしてこれが幸せに生きることだろうか?これを生きていると呼べるだろうか?これ以上に耐えがいことがあるだろうか?私は勇敢な人に語っているのでも高気な人に語っているのでもない。ただ普通の常識人に語っているのだ。自分の幸福も自由も体も他人に委ねるとはこんな悲惨な生き方があるだろうか?
自分というものを放棄した人間は自分の富も幸福も自由も、そもそも獲得しようがない。師はそのことに気がつかず自分を殺して生きることの愚かさを訴えます。ではもし圧政者から信頼を勝ち取ったとしてそれで安心して生きられるのでしょうか?もちろんそうではありません。歴史が示す通り圧政者の愛は極めて不安定であり、いつ裏切られ、奈落の底に突き落とされるかわからないのです。ボエシはその例としてローマの哲学者セネカをあげています。セネカは暴君ネロから厚遇されましたが最後はそのネロによって死に追いやられました。またボエシは暴君は最も近しいものによって殺されることが多いとも指摘します。つまり圧政者も側近もお互いを信じることができず、絶えず相手を恐れているのです。その上で彼は両者の間に決定的に欠けているものを指摘します。確かなことは圧政者は決して愛されることも愛することもないということだ。友愛とは神聖な名であり、聖なるものである。それは善人同士の間でしか存在せず、互いの尊敬によってしか生まれない。それは利益によってではなくむしろ良い生き方によって保たれるのだ。圧政者の財宝の輝きに目を奪われた側は自ら炎の中に飛び込んでいることに気がついていないのだろう。彼に気に入られることばかり考えながら彼を誰よりも恐れているとは何という苦悩だろうか。私は彼らに対する格別の罰を神が来世で用意してくださっていると確信している。
師は圧政者と側近たちの間には友愛が存在しないと主張します。友愛とは善良なもの同士の間で育まれる絆であり、それは互いへの敬意と誠実さによって支えられています。一方圧政者を中心とした人間関係は恐怖と打算に基づく共謀に過ぎないと言います。またボエシは友愛が成立する条件として平等を上げています。つまり支配するものとされるものという上下関係ではなく互いに対等であるという前提に立った時、初めて友愛が育つというわけです。また興味深いことにボエシは圧政者本人よりもむしろその取り巻きの方が悲惨な運命をたどると指摘します。というのも彼らは富や権力の代償としていつも緊張しながら相手の機嫌を伺い、裏切りや粛清の恐怖に怯える生活を強いられるからです。さらに側近たちは重税を課す、処罰を下すといったトップの命令の実行部隊であるため、民衆からは最も憎まれ軽別される対象となります。つまり圧政者の側近は旨味のあるポジションではなく上からは恐怖、下からは憎悪という、逃げ場のない二重の苦しみにさらされる極めて悲惨な立場なのです。ボエシはそれでもなお圧政者に近づこうとするものはもはや救いようがなく、神の裁きを待つほないと締めくります。社会秩序とは人間の生活に安定をもたらす一方で、自由を制限するという2面性を持っています。そのためそれを完全な悪として破壊すれば世界は混乱に陥り、逆に盲目的に従えば圧政の温床として腐敗を促進してしまいます。本書が問いかけるのはこうした矛盾を受け入れた上で、自分たちの社会システムを俯瞰し、最善と信じられる道をそれぞれが選択することだと言えます。
【名著】自発的隷従論|ボエシ 自分で自分を苦しめ、社会を腐敗させる「史上最悪の習慣」の抜け出し方。
アベノミクス 一番の問題は「ものづくり」に固執したこと?
アベノミクスにより世界5位から30位に転落した
日本人は国際的に低い給料の本質をわかってない

アベノミクスでトリクルダウンが起きなかった理由
国内に工場で生産した商品が、為替安で外国へ安くどんどん輸出され、企業の売上が伸び円還元した際には利益が大きくなる。もちろん国内工場従業員にも還元される。そういう外需で経済成長している国であれば為替安のメリットは大きい。でも現在の日本企業、例えば自動車産業であれば海外工場で、外国人労働者によって生産されその地域の国々に販売される。輸出の割合が減少し、現地生産の割合が増えている。もちろん為替安になれば、円還元した際には利益額は大きくなる。でもそれは「外国で生産し、外国で販売した外国での成果」なので、その利益が国内工場従業員に還元されることは無い。アベノミクスでトリクルダウンが起きなかった理由の一つがこれ。
コメ主の「為替安は国にとってメリットが大きい」 はどちらかというと「為替安は海外工場を持っている企業にとってはメリットが大きい」って感じ。
なぜか最近、為替は国力を反映しているという論調が強いけど、それなら東日本大震災の時に超円高に振れたことはどう説明するのだろうか? ハッキリ言って、為替レートはその時々の経済環境(金融政策など)による「結果」であって、単純に国力を反映するような代物ではない。 ちなみに為替安はその国にとってデメリットよりもメリットのほうが大きいとされる。だから中国は人民元を元安に誘導していたし、アメリカはそれを批判してきた。 目先の物価高に踊らされて円安を批判するより、円安によるメリットを見据えたほうが良いと思う。

儲からない製造業を推したことが原因?
「ものづくり」って誰も言わなくなったよね。

Twitter / Google / Youtube / 5ch / mimizun
/ リアルタイム / Google トレンド ものづくり
アベノミクス偽装 研究開発費など加え GDPかさ上げ
研究開発費などが加えられたため、GDPが大きくかさ上げされることになりました。アベノミクス以降を大幅にかさ上げし、1990年代を大幅に押し下げているということです。狙いはアベノミクスが成功しているように見せかけることです。
日本のギリシャ化=観光国化
アベノミクスって日本人に対する経済制裁だろ
日本崩壊をダメ押ししてんじゃねーか、アベノミクスw
失業率改善は「団塊世代の退職で労働人口不足」なだけ
失業率改善はアベノミクス関係ないよ。団塊世代の退職で労働人口が足りなくなることは1980年代から分かっていた。人口動態みてりゃバカでも分かる理屈。人が足りないなら新卒内定率も上がるし失業率も下がる。と少し頭のいい中学生でも分かることが、世間の大人の大多数が分かっていないことが恐ろしい。政府とメディアの持ち上げにまんまと乗せられて思考停止。そりゃ日銀に株買わせるわなw
労働者派遣事業をなくせば、手取りは今の3割は騰がるだろ
ピンハネをなくせば、末端の労働者の手取りは今の3割は騰がるだろ
楽天・三木谷氏「移民政策以外に手はない」
移民政策に対する不安は分かりますが、もはや他に手はないと思いますよ。幕末の攘夷論ではないけれど、現実を受け入れないと。人口減少する国に経済発展はないし、科学技術には国際的なトップクラスの人材を集める必要がある。その上で如何に日本らしさをキープするか。
日本企業が欲しいのは奴隷だけ
優秀な研究者を集めるとの、移民政策は意味が違う
ホワイトカラーからだと言ってるのに現実は実習生みたいなブルーカラーばっか
お前ら日本企業が欲しいのは奴隷だけってのが見え見えで、日本企業の給与体系で国際的なトップの人材なんて来るわけねえから不安なんだろうが
そもそも優秀な人材は日本を選ばない
そもそも優秀な人材なら斜陽日本を選ばない。もし選んだのならばそれは優秀な人材ではないってことだ。それがわかっているくせに移民しかないと主張するのは安い労働力がほしいということを誤魔化しているってこった
30年も発展しない国
発展しない時期が30年も続いているだぞw経済成長しない、ってことは、30年間、所得が上がっていないってことなんだぞwで、商売人でさえ、成長より幸福とか言ってたんだから、おめでたいよ、日本はw勤め人ならいざしらず、商売人がこれだから、終わってんだよw
観光しか売るものがなくなった国
- それな…凋落するばかりよ
- 悲しいなあ
- 情けない話だが、本当にもうそれしか無いんだから仕方が無い。背に腹は変えられん
- 外貨獲得手段が観光だけって…。先進国とは言えないな
- 円安で輸出額は多少増えたが、それ以上に輸入額が増えてとうとう収支が赤字に転落してしまったからな。観光でなんとか黒字に持っていくしかない
- ド田舎の無能議員しかいない赤字自治体を見てるようだな
「工業技術の時代」の終焉…次は「情報技術の時代」
(少なくとも先進国においては)「モノを巡る課題」の多くは解決され、工業技術の時代は終わり、情報技術の時代を迎えます。
それは、ディスインフレの時代でもありました。社会の課題がインターネットやプラットフォームなど「見えない課題」に姿を変えると、「イノベーションのジレンマ」や他国によるキャッチアップと共に、日本企業の時代も終わりました。
中国とアメリカのデカップリングで世界が変わった
日本の製造業が発展。中国は衰退。
“6つの未来” あなたはどれを選ぶ?
- 地方分散・マイペース社会
- 働けど貧困社会
- 現状維持社会
- 都市集中・格差社会
- 多様性・イノベーション社会
- 多様性・停滞社会
2024 私たちの選択~AI×専門家による “6つの未来”~【前編】
2024 私たちの選択~AI×専門家による “6つの未来”~【後編】

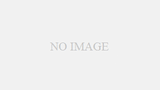
コメント