2025年08月17日 「きれいな海」と「豊かな海」は別 下水処理見直しシラス不漁解消へ
静岡市は、駿河湾でのシラス不漁の原因の一つとされる栄養不足の改善を目的に、安倍川河口近くの中島浄化センターで下水処理方法を見直した。従来は水質を可能な限り浄化する方針だったが、水がきれいになりすぎて栄養分が減り、植物性プランクトンから魚類まで生態系全体が痩せ細る問題が指摘されていた。
検証の結果、浄化タンクに送る空気量を調整することで、規制値を満たしつつアンモニア性窒素をより多く残せることが判明。これにより、これまで年間約40トンだった放流量を約90トンに増やすことが可能となった。さらに電気使用量が減り、年間約500万円のコスト削減効果も期待される。
このような「きれいな海」から「豊かな海」への転換は、瀬戸内海など閉鎖性海域では試みられてきたが、県内での実施は初めて。静岡市の難波市長は「すぐに漁獲量が改善するわけではないが、少しずつ積み重ねることが大切」と述べている。
要するに、海を単純にきれいにすることだけでなく、生態系に必要な栄養のバランスを意識し、豊かさを維持する方針へと舵を切った取り組みである。
2020年11月16日 大阪湾の透明度、上がれば上がるほど漁獲量減…プランクトン減りすぎてエサ不足
大阪湾では水質改善が進み、透明度が上がった結果として、魚の漁獲量が減少している。これは魚のエサとなるプランクトンが減少しすぎたことが大きな要因とされる。
背景には、高度成長期に工場排水や下水によって赤潮が頻発したため、国が窒素やリンなどの栄養塩を厳しく規制したことがある。規制の効果で海は美しくなったが、栄養が不足し、イカナゴなどの漁獲量が減少した。
その対策として、大阪湾では海底を耕すようにかき回す作業が行われ、栄養分を拡散させて魚のエサ環境を改善しようとしている。しかし効果は一時的で、規模の拡大や公的支援が必要であるとの声が漁師から上がっている。
一方、兵庫県は栄養塩を一定以上保つための下限目標を全国で初めて条例で定め、排水基準を緩和して漁獲改善を図っている。大阪府は市民の「海をきれいにしてほしい」という要望が強いため、現時点では同様の方針に慎重である。
研究者は、大阪湾の再生には「美しさだけでなく、栄養分を含めた海の豊かさをどう保つか」が重要だと指摘している。
要約すると、大阪湾は美しくなった一方で、魚が減るというジレンマに直面しており、環境保全と漁業資源の両立が課題となっている、という内容です。
整備された森は海に栄養や安定した環境を提供
整備された森が海の生態系に与える影響については、「魚つき林」と呼ばれる沿岸の森林の役割が代表的です。魚つき林は直射日光の遮断や風波からの保護を通じて水温の安定化を促し、微生物の発生や栄養塩の供給を促進して海の生物の繁殖に有利な環境を作り出します。この結果、豊かな森があることで沿岸の生物多様性が守られ、魚が多く生息する環境が維持されることが科学的に示されています。
また、森林は洪水や渇水といった水量の極端な変動を和らげ、河川から流れ込む土砂や微細粒子を減らして海の生態系への悪影響を防いでいます。これらの作用を通して、森は川を経て海に栄養を送り、海の生態系全体の生産性を高めています。
日本各地では漁民や行政、市民が協力して「漁民の森づくり活動」を推進し、魚つき林の維持・管理に取り組むことで豊かな海づくりを実現しています。こうした連携が持続可能な海の資源保護に寄与しています。
まとめると、整備された森は海に栄養や安定した環境を提供し、魚の生息に適した豊かな海を育む重要な役割を果たしています。森と海は密接に連携しており、このつながりを守ることが豊かな漁場の維持につながっています。
私が幼いころはし尿を餌代わりに撒いてました
瀬戸内海の場合は、近年水がきれいになりすぎて、窒素・リンなどの栄養も足りず、プランクトンも育ちません。よって、カキ、アサリ、エビ、魚が、激減しています。私が幼いころは、カキいかだの周りに、し尿を餌代わりに撒いたりしてました。今は、そんなことをすることはありませんし、下水の浄水できれいにしすぎた水を海に流すので、栄養は海に残りません。見た目がきれいな海は、気持ちのいいもんですが、海の動植物にとって餌なしの過酷な海になっています。昔は、養豚場から、し尿が垂れ流ししていた時代は、赤潮が発生して、プランクトンがたくさん。魚も豊富でした。何が海の生物にとって良い状態なのかを、研究していただきたい。
鳥羽のカキ、3季連続大量死か 初水揚げの5割超、肩落とす業者
昔は川が氾濫することでさまざまな栄養素が海に届けられていました
昔は森も豊かでしたし、時々、川が氾濫することでさまざまな栄養素が海に届けられていました。今は、川を固めているため供給される栄養素は限定的になっているとは言われていたと思います。瀬戸内海などはキレイで貧栄養になりすぎたため、赤潮の心配の無い冬季には、下水処理を緩めに行ったり、一部をほとんどそのまま放出したりすることで栄養素を海に供給しようとし始めているそうです。
三期連続でカキが6割~8割も死滅
三期連続でカキが6割~8割も死滅するなんて何が原因なんだろう。これが続くと死活問題だろうし、専門家に早急に原因を究明して貰いたいとろです。需要と供給のバランスが崩れて値上がりするでしょうね。
成長が悪いのでなく死んでいる
成長が悪いのでなく死んでいるのは訳がわからない。赤潮などの発生もないし。水産試験所は、他県の力を借りてでも、原因究明して欲しい。
牡蠣は、山から流れてくる栄養で育つ
牡蠣は、山から流れてくる栄養で育つと聞いたことがあります。天候の変化や温度、水温などの変化もあるのでしょうか。
綺麗すぎて栄養がなくて魚や貝が育たない
近年、海を汚すなと浄化運動が盛んに行われてますが、ある程度の汚れがないと綺麗すぎて栄養がなくて魚や貝が育たないそうです。そういった水質の変化なんかも影響があるんじゃないでしょうか。
適当に海面上に出させ、ゆっくり育てる必要がある
カキは育ちすぎも悪いと聞く。人工の筏では、干出がなく、餌が多くてすくすく育つが、育ちすぎると餌が少ない時に、代謝が大きすぎて、エネルギーを消耗してしまい、死んでしまう。
自然の岩場のように、適当に海面上に干出させ、ゆっくり育てる必要があるのではないか。
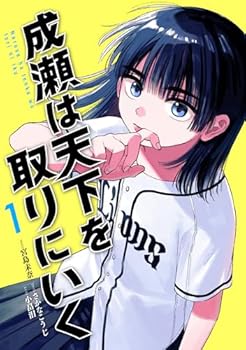
コメント