ペロブスカイトの実用化、実用度
ペロブスカイト太陽電池の実用化は2025年から2026年にかけて少量の商用化が始まる段階で、街中への普及は約10年かかる見込みです。日本の積水化学など一部企業が2025年に事業化を明言し、JR西日本うめきた駅や東京都の水再生センターで実証実験も進んでいます。しかし、実用化の本格的な普及は2030年から2040年頃と見られています。
実用化に向けての課題は以下です。
- 鉛の使用:
人体や環境に有害な鉛が含まれており、廃棄や排出に関する規制の問題がある。 - 耐久性:
現時点で5~10年程度の耐久性であり、25年以上使用が求められる住宅用太陽光には耐久性が不足している。 - 社会的課題:
従来の太陽光発電では設置場所や景観、安全面、廃棄問題などがあるが、ペロブスカイトは軽量で柔軟、設置場所の制約が少なく低コストである点が期待されている。
総じて、ペロブスカイト太陽電池は軽量・柔軟・低コストが特長で、広い市場展開が期待される一方で、環境規制や耐久性の課題克服が必要で、2030年代の普及を目標に実証実験や量産体制整備が進んでいます。住宅用を含む多用途展開にはもう少し時間がかかる見通しです。
2025年10月18日 再エネの発電設備、日本製停滞 海外メーカー高いシェア
再生可能エネルギーの発電設備における日本製のシェアは停滞しており、太陽光パネルの国産割合は2012年の69.9%から2022年には11.6%まで大幅に減少しています。主因は価格の安い中国製の台頭で、日本企業は市場撤退や苦境に立たされています。一方で住宅用太陽光パネル市場では、純国産の長州産業が強い存在感を持ち、2025年では住宅用市場の国産シェアが約5割に回復しているとの報告もあります。
経済産業省は2030年代に洋上風力設備の国内調達率65%以上を目指すなど、自給率向上を掲げていますが、輸送コストや円安の影響、海外メーカーの競争力の高さにより、国産設備の普及は依然として厳しい状況です。
まとめると、発電設備全体では日本製の国産シェアはまだ低いが、住宅用太陽光パネル分野では長州産業など国産メーカーが一定の存在感を示しており、国としては国産化推進に向けて政策的支援や産業誘致を進めている段階です。
なぜ太陽光パネルだけことさら鉛を問題視するのか
鉛は太陽電池だけではなく、他の電化製品や自動車にも使用されています。それらの処分は普通に行われています。太陽光パネルだけことさら問題視する意味がわかりません。鉛は太陽電池に限らず、以下のように幅広い製品で使われています。
- 自動車用バッテリー(鉛蓄電池)
- 電子機器のはんだ
- 光学ガラスやケーブル被覆
- 一部の防音・防振材
こうした製品は古くから存在しており、回収・再利用の仕組みもある程度確立されています。
一方で、太陽光パネルが特に注目されるのは、以下のような背景があるためです。
- 今後、大量廃棄期(設置から20〜30年後)が一斉に到来する
- 家電製品や車のように回収ルートが整っていない地域が多い
- モジュールの破損(風災・地震など)で鉛やカドミウムが漏出する懸念
- 廃棄費用や処理責任の所在が不明確な場合がある
つまり、「鉛を使っていること」自体よりも、「大量かつ長期的に分散設置され、まだ統一的な回収体系が未整備」という構造的な問題が、太陽光パネル特有の懸念として指摘されているのです。
2025年10月18日 中国がクリーンエネルギーの世界的イノベーターになれた理由 特許出願数で日米欧を突き放す
この記事は、中国が「模倣国家」としての印象から脱し、クリーンエネルギー分野で世界的なイノベーターとなった背景を分析している。主な内容は以下の通り。
中国は2000年において、国際競争力を持つと評価されたクリーンエネルギー関連の特許が18件しかなかったが、2022年にはその出願件数が5000件を超えた。これは日米欧を大きく上回る伸びであり、特に再生可能エネルギー分野での存在感を急速に高めている。
欧州特許庁のチーフエコノミスト、ヤン・メニエールによると、特許の質を測る最も重要な指標は「どれだけの費用をかけて特許を守ろうとしているか」であり、複数国で出願することでその意志が示されるという。この基準をもとに分析した結果、中国は2022年時点で米国の2倍もの「質の高い特許」をクリーンエネルギー分野で出願していた。
中国では依然として既存技術と重複する特許申請も多いが、同時にオリジナル性や国際的競争力を持つ特許も増加しつつある点が注目される。欧州特許庁がニューヨーク・タイムズに提供したデータは、中国が単なる模倣者から真の革新主体へ変貌した実態を裏付けるものとされている。
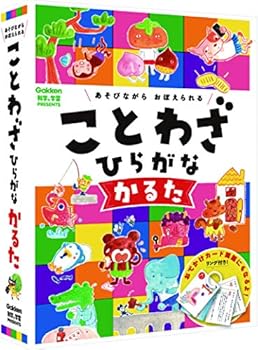
コメント